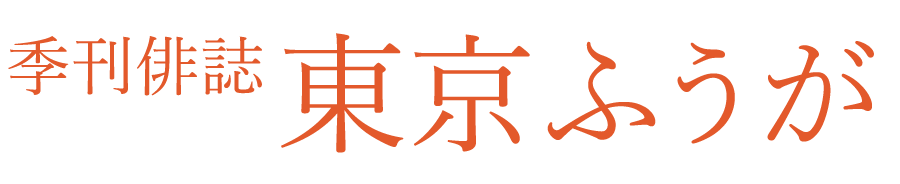コラム はいかい漫遊漫歩 『春耕』より
松谷富彦
126 新興俳句、何が新しかったのか ⑴
俳句結社集団の一つ、現代俳句協会の70周年事業として協会青年部(神野紗希部長)の手で2018年12月、『新興俳句アンソロジー 何が新しかったのか』(ふらんす堂刊)が出版された。 そもそも新興俳句は、水原秋櫻子が俳句創作に関して「自然の真」と「文芸上の真」の違いを主張し、高浜虚子の「ホトトギス」を脱会、自俳誌「馬酔木」を拠点に虚子俳句に対抗する創作活動を打ち出したのが、出発点。『新興俳句アンソロジー』の「序」で、現代俳句協会副会長の高野ムツオは書く。
〈 秋櫻子の主張の新しさは、表現者としての、言葉の働きへの意識化にあった。「『文芸上の真』とは、鉱(あらがね)にすぎない『自然の真』が、芸術家の頭の溶鉱炉の中で溶解され、加工されて、出来上がったものを指す」と述べている。ここには文芸とは言葉によって成立する世界であるとの大前提がある。言葉は「溶鉱炉」という表現主体を通じて生み出されるという認識に支えられていた。このことにもっとも鋭敏に反応したのは高屋窓秋であった。
この句は昭和7年1月号の「馬酔木」の雑詠に《 わが思ふ白い青空と落葉ふる 》など「白い」をテーマにした他の三句とともに並んでいる。俳句は言葉で作るとの明確な意識が感じられる。それは選んだ秋櫻子も承知していたに違いない。季題と次元を異にした発想なのは明白であった。〉と高野。
窓秋の句の新しさを最初に指摘したのは、石田波郷と言う。高野ムツオの文章を続けて引く。〈(窓秋の)句を端緒にして、多くの俳人が俳句には未知の鉱脈がいまだ無限に潜んでいると気づいたのだ。新興俳句の幕明けである。以後、戦争という社会的不安をも背景に、花鳥諷詠の世界に飽き足らない若い俳人を中心として、ときに瑞々しく、ときに鋭利にさまざまな作品が花開いていった。同時に問題も提起した。無季や抽象化などはその一つである。〉と高野は書く。
高屋窓秋本人は「俳句の表現」をどう考え、作句していたか、俳誌「現代俳句」(1950年3月号)に寄せた一文から抜き書きする。
〈 表現とは、外界の存在を、言葉に写しとることではない。それは、心に映じた直観像をそのまま言葉に直すことでもない。言葉に、そんな能力はない。言葉は、それ自身映像をもつものであって、詩は、それの特異な構造物だ。〉