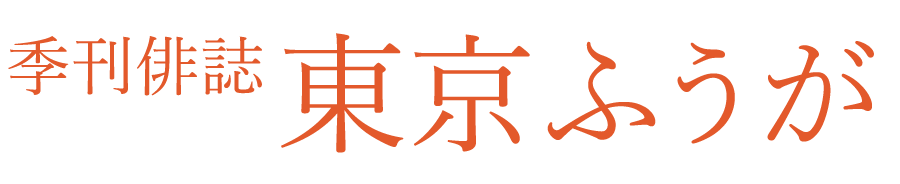「素十名句鑑賞」 20
蟇目良雨
(168)
寺清浄 僧等清浄夏めきぬ 昭和51年
昭和51年復刊「芹」掲載。紅花編著『素十俳句365日』8月11日の項に出ている。石井双刀の鑑賞を見て見よう。
「昭和51年5月29日、高尾山薬王院で催された「芹」復刊五周年記念大会出詠句。
この日素十は病を押して会衆の前に姿を見せた。筆者はその様子を一見して容易ならざる状態を直感し、こみ上げてくるものを制止できなかった。自らの予後を知る素十の、門下への訣別ではないかと推測したのである。素十は句会の席へは出ず、会衆大勢を見渡して何度も何度も深く頷いていた。
一句はそんなことには触れていない。高尾山一山あげてすがすがしく美しく、数多の僧たちも悉く清浄、いよいよ夏らしくなって行くとだけ言っている。初夏の日ざしと風とが心地よい日であった。そしてその後素十は門下の前に出ることはなく、四か月後の十月四日大いなる生涯を終えたのである。 」(双刀)
双刀の鑑賞文から明らかなように、最後の俳句大会に参加したのだが、虚子なら参加した連衆のことに触れたはずだが、素十は寺と僧の清浄さについて触れただけである。ここに素十の潔癖さを見ることが出来る。連衆との一体感も大切だがそれ以上に大切なのは、時代に左右されない寺院のあり方である。清浄な寺に正常な僧が居ればそれで充分であることを素十は確認しているのだ。ここに美辞麗句は必要ではなかった。