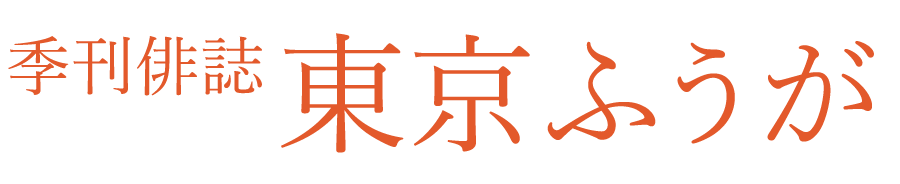小説 002「箱の中」
関野みち子
指定された店の前に立つと、雅代は小さくひとつ深呼吸をした。ついでに手のひらに息を吹きかけて口臭がないかを確認する。部下の女性社員と話をしている時に、相手がさりげなく鼻を押さえていることが最近になって幾度かあった。年齢による体の変化は、それだけではない。血圧、肌のタルミ、老眼も少し出てきたようなのは一ヵ月前に受診した会社の健康診断の場で指摘されていた。正式な検診結果はまもなく郵送で届くはずだから気にはなるが今から案じても仕方がない。それよりも楽しいことを考えようと雅代は頭を切り替えた。プライベートで男性と会うのは何年ぶりだろう。年甲斐もない高揚感にひとり赤面しながら雅代はお腹の贅肉が目立たぬようにと背筋を伸ばして店に入っていった。チェーンの居酒屋の店内は若者たちとサラリーマンの集団であふれていた。男が一人、奥のカウンター席から手を振っている。
「遅くなってごめんなさい」
席につくと雅代は詫びた。広告代理店のベテラン営業ウーマンである雅代は比較的時間の融通がきくが、その分、クライアントの都合で残業することも多かった。そのことを想定して指定した時間ではあったが、約束より二十分も遅れていた。
「もう来てくれないのかとドキドキしてましたよ。始まる前に振られてしまったのかなと」
雅代のために席を作ってくれながら神室はメニューを差し出してきた。勘定はワリカンにすればいいとメニューから自分の食べたいものを数品、雅代は選んだ。
「今夜は一段ときれいだな。こんな美人とデートできるなんて齢はとってみるものだ」
歯の浮くような神室のお世辞に小娘じゃあるまいしと雅代は少し鼻白んだ。奥二重の目に低くも高くもない鼻、薄い唇と一つ一つをとれば日本美人と言えなくもないが、いかつい顔の輪郭がそれを邪魔しているのを雅代は知っていた。子供を産んでいないせいかスリーサイズは二十代の頃のままというのが唯一の自慢と言えなくもないが、それもこの頃はあやしくなっている。しかし職業柄、美容関係のクライアントとのつきあいが多い雅代は、自分の欠点を隠すお洒落に長けていた。今日も顎の線を隠すようにカットしたセミロングのヘアスタイル、ウェストを絞ったネイビーブルーの麻のスーツという装いで欠点と年齢を巧みに隠している。昼食を食べそびれた雅代の食欲は旺盛だった。神室はと言えば、さっきからほとんど食べ物には箸をつけないで嘗めるようにビールを飲んでは雅代の私生活に探りを入れてきていた。居酒屋という場所を指定してきたことといい、この男、案外吝嗇かもしれないと密かに相手を値踏みしながら雅代は料理を次々と口に運んではビールを呷った。神室と知り合ったのは三ヶ月前のことだ。雅代が出席した異業種交流セミナーで隣の席になったのが彼だった。そのセミナーの指導法は変わっていて隣り合った参加者同士がレポートをチェックするという方法をとっていたが、時間内に雅代も神室もレポートを仕上げることができずカフェで二度ばかり会って仕上げたのだった。雅代の自己紹介に神室は悠々自適の自営業と言うばかりでそれ以上語ろうとしなかったし、雅代にとっても仕事の延長であり、あえて聞こうとも思わなかった。そしてレポート完成の打ち上げをということで神室が誘ってきたのが今日の席だった。
テーブルに並んだ刺身やサラダの器があらかた空になった頃、二本目のビールを雅代のコップに注ぎながら神室が突然言った。
「今度、すき焼きをしませんか。僕のマンションで」
唐突な言葉の意味を理解するのに雅代は少し時間がかかった。
「すき焼き、ですか」
「部屋はボロですがね。眺めがね、きれいですよ。百万ドルの夜景って言われてます」
あまりに性急な展開に、雅代は内心苦笑しながらやんわりと言った。
「そんなことできっこないじゃありませんか」
「そんなことって」
「男の人の部屋に行くことですよ」
「だってあなたも僕も独身じゃないですか。なんの障害があるんです?」
雅代はカウンターに落としていた視線をさりげなく神室に向けた。顔色こそ変わってないもののからんでくるような目つきがあやしい。あれしきの酒で酔ってしまっているのだ。
「神室さんと会ったのは今日で三度目よ。若い人じゃあるまいしだめに決まってます」
きつくなった言葉尻をごまかそうと雅代は小さく笑った。それに失礼な男ではあるが四十八歳の女にとって男に誘われる経験はそう度々あるものではない。正直いって悪い気がしなかった。神室の口調が改まる。
「そういうことではだめだな」
「何がだめなの」
骨張った体を遠慮なくこちらの肩に傾けてくる神室を避けながら雅代は言った。口調が弾んでいるのが自分でも少し忌ま忌ましかったが、しかし次に神室が発した言葉が雅代の浮き立つ心を見事に打ち砕いた。
「須崎さんね、今からそんなじゃ介護されるようになったらどうするの。いやでも体に触られるんですよ」