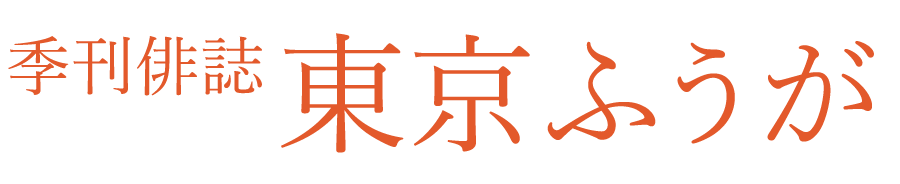「素十名句鑑賞」19
蟇目良雨
(161)
いかにせんおん墓石の冷さを 昭和36年
虚子の三回忌に当たっての感懐である。虚子の墓石に触れて感じる冷たさを、いかんともし難いと嘆く素十である。虚子が亡くなってから素十は、虚子に代わって意見を求められる立場に置かれた。写生や花鳥諷詠のことについて虚子の考えを述べるにしても、決して虚子の域に達することが出来ないことを知っていた。墓石にすがっても知りたい虚子の言葉がまだあるのである。
(162)
鍋焼のいまの二人は芝居もの 昭和37年
うどんも蕎麦も、今では専門店化して、同じ店で両方注文することは難しいかもしれない。鍋焼きうどんは冬の当り商品なので、蕎麦屋に行けば殆ど注文できた。一人用の寄せ鍋の鍋に煮え立ったうどんと具をふうふう冷ましながら食べる楽しみは、まさに冬のものである。目を巡らせると鍋焼うどんを食べている二人連れが見える。背筋をきりっと張った姿勢や箸の使い方も様になっている。きっと近くの芝居小屋から来た役者なのだろうと納得したのである。
鍋焼うどんは贅沢になると「うどんすき」になる。こうなるとお座敷に入らなければ食べられなくなる。昭和30年代ということを考えると、町の蕎麦屋での光景と思われる。
(163)
菜虫とる我生涯もこのへんか 昭和41年
素十は73歳になった。奈良医科大学に勤めた翌年から京都市山科区逗子奧に居を構えた。脳溢血で発病するまで、ここに住み続けた。湖西線山科駅に近く、まだ閑静なたたずまいであった。裏には家庭菜園があり、畑仕事も楽しみの一つになっていた。虚子亡きあとホトトギス俳句を代表する立場になり、各界から声がかかって忙しい身であった素十だが、家庭菜園で菜虫を取っている自分を客観視して、今が人生で上々の時だと呟いている。決して奢った言い方でなく、真実そう思ったことと私は思う。