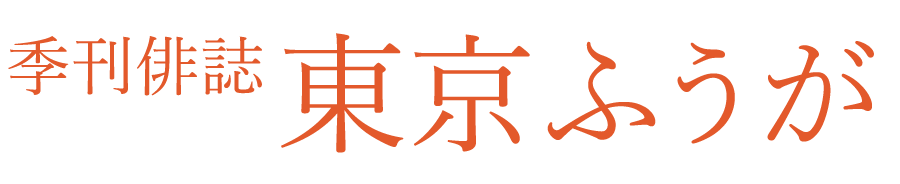小説 001「春子と春子」
関野みち子
地下鉄の動物園前駅で降りると異臭がした。階段をあがる度に臭いは強くなる。小便の臭いだ。踊り場で立ちどまると俺は、顔を上げた。早春の空が広がっていた。
「おう――」
地上につくと、思わず声が出た。東の方角にあべのハルカスが見えた。日本で一番高いビルが、天を突き刺すように聳えている。道を通る人をつかまえて言いたくなった、あれは俺が作ったんだと。ばかでかい箱の中で、着飾った女たちが買い物をして、子供達がはしゃぎ回り、スーツ姿のサラリーマンが商談をしている姿を想像してなんだか誇らしくなった。
ついこのあいだまで俺は、あの下で働いていた。工事現場の夜回りだ。元々、大手ゼネコンの下請けの下請けの、そのまた下の作業要員として日本全国を渡り歩いてきた。六十歳を過ぎ体力が続かなくなったのを機に、会社と相談して地元に帰り、雑用係兼守衛として雇ってもらった。六年前のことだ。ハルカスは最後の現場だった。
仕事に行く俺にヨメはんは、毎日弁当を作ってもたせてくれた。一緒に働く奴は、うまそうに弁当を食べる俺を見てからかったが、平気だった。ところが、ある日を境に弁当のおかずがだんだん貧弱になった。そして毎日の弁当が、二日に一回になり、一週間に一回になり……。三ヶ月前、とうとうヨメはんは天国へ旅立っていった。膵臓ガンだった。
ホームレス風の老人が二人、詰将棋に興じるガード下をくぐるとジャンジャン横丁に出た。
「一杯ひっかけていくか」
誰にともなく言うと串カツ屋に入った。ドテ焼きを凍る寸前の生ビールで流し込むと、俺は再び歩きだす。
ペンギンやライオンやキリンが描かれた入り口の前に立った。チケット売り場には人だかりができていたが、年金暮らしの俺にとって六十五歳以上は無料というのは有り難いシステムだ。受付に置いてあった地図を頼りに目的地を探す。
「あった!」
檻の見える方へ、思わず駆け出していた。心を鎮めて、まずは説明書きから読んだ。
春子。アジア象。メス。原産地・タイ。二歳の時に来日。六十六歳は日本で二番目に高齢。
えらいやっちゃ……俺はつぶやいた。すでに涙腺が緩くなっている。二歳の時にタイから、戦争が終わって間もない日本に連れてこられた春子。象を見たことがない日本人が多かった時代から、こいつは頑張ってきよったんや。そう思うとヨメはんの顔が浮かんできた。春子という名前も、年齢も一緒だった。