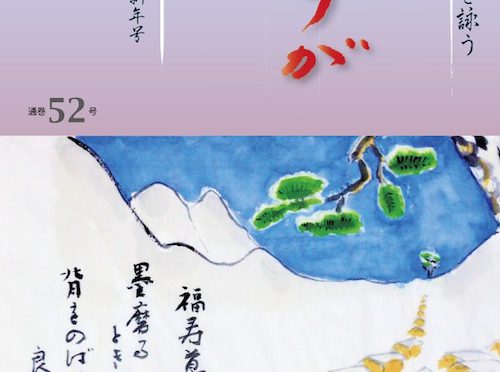寄り道高野素十論 22
蟇目良雨
101 ─ 素十と紅花 ─
平成 30年角川「俳句」二月号は「高野素十の写生」特集であった。現在、高野素十研究の第一人者「雪」主宰蒲原ひろし先生の話を岸本尚毅が聞きだすといものである。会場は新潟市の「かき正」。かつて私もここで蒲原先生のお話を伺ったことがありなつかしさを感じた。
大正12年生れ満94歳の蒲原先生の脳は益々冴えわたっていて引き込まれること度々であった。
高野素十のことは何度聞いてもその魅力が薄れることが無く人物の大きさを益々感じさせることを再発見したのである。先生におかれてはお元気で高野素十研究を進めていただきたいとつくづく思った。
「俳句」には関係者の随筆が何遍か掲載されている。その中で星野椿さんの「私にとっての素十 金風居士素十」と言う文章に興味ある記述があることを発見した。
一、素十は十月に亡くなったので金風居士と命名された。私もこの戒名から句集を『金風』という題名にした。
二、私は子供の頃から母と一緒に度々会っているので「オランウータン」等と呼んで親しかった。
三、素十はいつも何処かで見守っていてくれる様な存在で私にとっては不思議な憧れにも似た思いがふつふつと湧いてくる。
四、素十が虚子を時々親父と呼んで、おこられた等と敬愛している姿は忘れられない。
五、京都では度々虚子と句会をしていて、夜等宴会の後も、猶飲み続ける素十に虚子が「早く寝なさい」と言うとまるで子供のように布団にもぐり込んだのよとよく母から聞かされていた。
ここには虚子を親父のように思い、自由に振舞っている素十がいる。久女に対しての冷徹な態度と素十に対しての大甘の態度の落差はどこから来るのだろうか。不思議である。
前回まで私は、杉田久女の悲劇に至る遠因に立子の自立を進める虚子の態度について論を進めて来た。
その論拠は、かつて村松紅花先生が私と畏友稲田眸子氏に漏らされた「素十と立子の間に出来た子が椿さんだ」という話が前提に立っている。幼い椿を抱えた立子の身過ぎ世過ぎのために「玉藻」を創立し、「玉藻」の発展を阻みそのライバルになろうとするだろう杉田久女の力を封じ込めようと、久女が希った句集出版の依頼を悉く潰したことが久女の悲劇につながったというストーリーである。
虚子が還暦を迎え立子の将来を真剣に心配した高浜家の事情が裏にある。
昭和5年に椿が生まれ、昭和6年に「自然の真と文芸上の真」論争を秋櫻子が素十を相手に一方的に仕掛けて「ホトトギス」を飛び出し、「客観写生」を砦とする「ホトトギス」の牙城を脅かした時代に、久女までが句集を上梓して少なくとも女流俳人をかっさらって行くのではないだろうかと恐れ、虚子が立子の生活の安定を願って久女の句集出版を許さなかったという筋書きはあながち荒唐無稽ではないと私は思う。久女が句集出版を求めて虚子に会うために上京したのは昭和九年の頃である。翌十年には山口誓子が橋本多佳子を連れて「ホトトギス」を離脱したという「ホトトギス」にとっては危機を肌身に感じていた時代なのである。
村松紅花先生はなぜ私たちにこんな裏話をしてくれたのだろうか。原点に立ち戻って先生とお話した時のことを再録してみる。先生は二年後の平成21年3月16日に8ヶ月の入院生活を経て永眠なさってしまった。享年88であった。
最近新しい読者が増えて上記のいきさつが曖昧になったこともあり再録したものである。