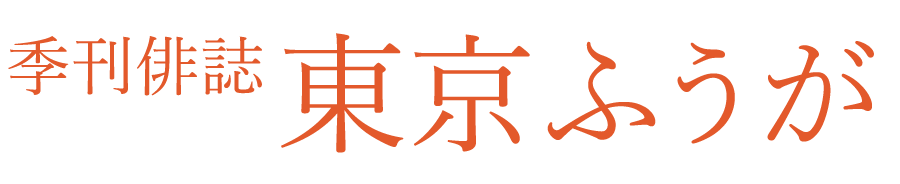俳句鑑賞「墨痕三滴」– category –
-

秩父路に電車の響き桃節句
高木良多講評 東京ふうが 平成26年 春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報347号~348号より選 秩父路に電車の響き桃節句 元石一雄 秩父は山が連なっているので電車が... -

よく動く蟹を選りをり年の市
高木良多講評 東京ふうが 平成26年 冬季・新年号「墨痕三滴」より お茶の水句会報344号~346号より選 よく動く蟹を選りをり年の市 石川英子 上五「よく動く」の説明が... -

夏服の女子学生や鑑真廟
高木良多講評 東京ふうが 平成25年 秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報340号~343号より選 夏服の女子学生や鑑真廟 井上芳子 鑑真は唐の学僧で日本律宗の祖。七五... -

縁に干す母の紬や更衣
高木良多講評 東京ふうが 平成25年 春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報337号~339号より選 縁に干す母の紬や更衣 乾 佐知子 お母さんの着ていた大事な紬織りの... -

赤シャツは父の目印潮干狩
高木良多講評 東京ふうが 平成25年 春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報335号~336号より選 赤シャツは父の目印潮干狩 鈴木 大林子 潮干狩はお天気が良ければ大... -

硝子戸の中の門松丸の内
高木良多講評 東京ふうが 平成24年 冬季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報332号~334号より選 硝子戸の中の門松丸の内 蟇目良雨 どんな貧しい家でも門松は門の内か外... -

潮の香の押しくる荒磯神の留守
高木良多講評 東京ふうが 平成24年 秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報329号~331号より選 潮の香の押しくる荒磯神の留守 堀越純 上五、中七までは平凡な写生であ... -

緑蔭に身を反らしゐる大道芸
高木良多講評 東京ふうが 平成24年 夏季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報325号~327号より選 緑蔭に身を反らしゐる大道芸 花里洋子 大道芸人が何かの芸のため... -

遠足の子らに風鐸鳴りやまず
高木良多講評 東京ふうが 平成24年 春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報322号~324号より選 遠足の子らに風鐸鳴りやまず 深川知子 風鐸が鳴りやまずであるから風の... -

綿虫の湧く峠路の没り日かな
高木良多講評 東京ふうが 平成24年 冬季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報318号~321号より選 綿虫の湧く峠路の没り日かな 石川英子 綿虫と峠路と没り日で情景がは... -

新豆腐入荷と墨書なんでも屋
高木良多講評 東京ふうが 平成平成23年 秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報316号~318号より選 新豆腐入荷と墨書なんでも屋 元石一雄 田舎のなんでも屋の店... -

親子して探し物あり柿若葉
高木良多講評 東京ふうが 平成23年 夏季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報313号~315号より選 親子して探し物あり柿若葉 井上芳子 親が何かを探している。子の私もま... -

春雷やもろみの眠る仕込蔵
高木良多講評 東京ふうが 平成23年 春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報311号~312号より選 春雷やもろみの眠る仕込蔵 乾佐知子 「もろみの眠る仕込蔵」と春... -

立春大吉鉱泉宿に兜太の書
高木良多講評 東京ふうが 平成23年 冬季・新年号「墨痕三滴」より お茶の水句会報307号~310号より選 立春大吉鉱泉宿に兜太の書 鈴木大林子 「兜太の書」は現代俳句協... -

真葛原風の荒ぶる吉野みち
高木良多講評 東京ふうが 平成22年 秋季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報304号~306号より選 真葛原風の荒ぶる吉野みち 積田 太郎 吉野みちは天智天皇から... -

筒鳥や崖に張りつく御師の家
高木良多講評 東京ふうが 平成22年夏季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報302号~303号より選 筒鳥や崖に張りつく御師の家 荻原 芳堂 御師の家とは山岳宗教... -

名の木の芽ひとつひとつに雨雫
高木良多講評 東京ふうが 平成22年春季号「墨痕三滴」より お茶の水句会報298~301号より選 名の木の芽ひとつひとつに雨雫 蟇目 良雨 名の木の芽はたとえばし...
12