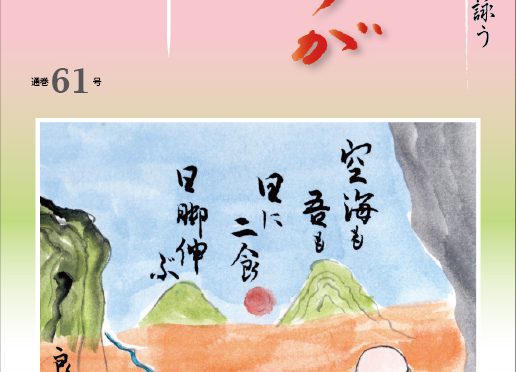コラム はいかい漫遊漫歩 『春耕』より
松谷富彦
114 「いかに美しく消耗するか」の覚悟で詠む(上)
平成時代が31年をもって幕を閉じた。この時代を回顧する本が次々に登場することだろう。その先陣を切り、予め定められた時代の区切りにタイミングを合わせて刊行されたのが、『俳句の水脈を求めて ― 平成に逝った俳人たち』(角谷昌子著 角川書店刊)。
〈 昭和を生き、平成に逝った26俳人の作品と境涯。彼らはどのように俳句と向き合い、何を俳句に託したか。そのひたむきで多様な生と、魂の表現としての俳句の水脈を探る。〉と帯文が謳う同書に登場の女性俳人は、飯島晴子、野沢節子、桂信子、中村苑子、細見綾子、津田清子、鈴木真砂女の七名。
この中から生涯を「いかに美しく消耗するか」の覚悟で俳句を詠み続けた細見綾子の境涯を自らも俳人として同時代を生きて来た著者、角谷昌子の簡潔な記述を引きながら、辿ってみる。
角谷は、綾子の章に[天然自然の柔軟性]のタイトルを付し、〈 中村草田男の向日的な句風を、塚本邦雄や楠本健吉らは「能天気」と評した。綾子の第一句集の口誦性豊かな《うすものを着て雲の行くたのしさよ》《チューリップ喜びだけをもってゐる》《つばめつばめ泥が好きなる燕かな》を私は愛誦しながら、どこか同じような印象を抱いていた。だが作品を読み込み、境涯を知って、草田男の場合と同様に、綾子俳句を「能天気」とみる思いは払拭された。〉と書き起す。「能天気」に似て非なる綾子の「独自の詩心」に気付いたと言うのだ。
綾子の20代は、過酷な青春に包み込まれる。現在の兵庫県丹波市青垣町の富裕な農家の長女として生まれた。〈 吉屋信子のような小説家になりたいと母を説得 〉し、日本女子大に進んだ綾子は、20歳で卒業。すぐに東大医学部の助手、太田庄一と結婚。だが、2年の結婚生活で夫は病没、実家に戻った綾子を待っていたのは、母の死と兄弟の事業の失敗による実家の差し押さえ、そして自身も肋膜炎を発症して病臥の身に。
俳句を始めたのは22歳で、松瀬青々の「倦鳥」に初入選し、同年投句の〈 来てみればほゝけちらして猫柳 〉が巻頭を取る。角谷の記述を引く。
〈 綾子は当時を振り返って、青々は「生きる魅力と涙」をよく知っている人物であり、師の「俳句の甘美」がなかったら、自分は俳句を作っていなかったと断言する。すべてのものが「空虚」かつ「蕭条」としてぽっかり虚無の口を開けている。そんななか、青々俳句の優しさは命を吹き込む泉の水だった。〉
綾子が終生の伴侶、句作の同士となる沢木欣一と初めて会ったのは昭和17年、欣一はまだ東大の学生だった。綾子は紅葉の名所、箕面に欣一ら三人の大学生を案内する。〈 そのとき、学生たちは近いうちに戦地へ赴かねばならず、それまでいかに生きればよいか話し合っていた。〉と角谷は書く。
(敬称略 次話に続く)