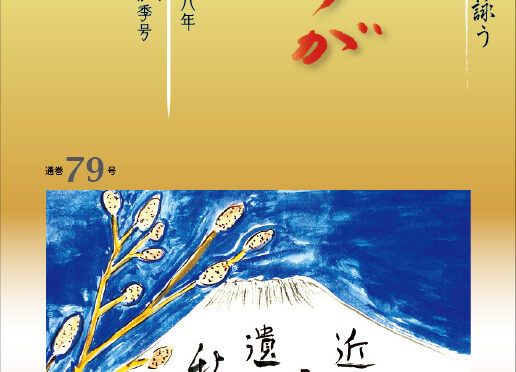「素十名句鑑賞」 17
蟇目良雨
(141)
稻車覆りゐる小ささよ 昭和22年
稲車は稲束を積んで運ぶための運搬車。いろいろな形がある。稲束を堆く積んだトラックから、細い畦道を抜けるための猫車と呼ばれる一輪車も、稲束を運ぶためなら稲車である。稲を運ぶ途中に覆っている稲車を見ると何と小さかったかと驚いているのが掲句であり、素十の観察眼の確かさが窺える作品だ。何故覆ってしまったのか、何故小さかったのかなど想像すると、現場の景色がありありと見えて来る。細い畦道であるので猫車を用いたところ、余りにも凸凹している路面なので、ついひっくり返った光景を目撃したに違いない。
(142)
冬山に吉野拾遺をのこしたる 昭和23年
鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇と足利尊氏は、京都に幕府を移したが、後醍醐天皇の政治に不満を持つ尊氏ら武士は替りに光明天皇を践祚した。これに不満をもった後醍醐天皇は、吉野に逃れて南朝を建てた。以後約六十年、南朝と北朝に分かれて二人の天皇が立つ南北朝が出現した。その内、後醍醐天皇の二十数年間の吉野時代を著した書を『吉野拾遺』という。素十は冬の金峰山寺を訪れて、後醍醐天皇の吉野時代を偲んでいるのである。冬山の厳しい季節を如何にお過ごしになられたかは、『吉野拾遺』を読めば理解出来るはずだと素十は思っている。冬山だからこそ、同情も一入であったことだろう。
(143)
ガスの町樺太犬は車ひく 昭和23年
ガス=海霧
ガスは海霧のことで、素十は敢えてこの語を用いた。昭和23年6月に虚子らと氷川丸で北海道に渡り、各地を旅行した時の作品。樺太犬が橇を引く光景なら驚かないかも知れないが、車を引いているところに違和感を持った素十の観察眼がこの句にはある。戦後の作品であり、樺太はもうソ連に取られていた時代だ。引揚者が樺太犬を北海道に連れて来て、冬は雪橇を引かせ、それ以外は荷車や人の乗った車を引かせて、生活の足しにしていると思われる。時代を敏感に記録している句だ。
(つづきは本誌をご覧ください。)