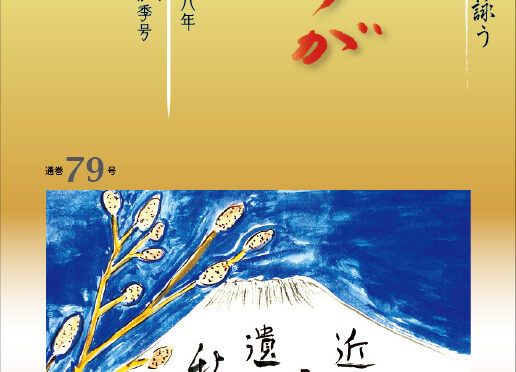歳時記のご先祖様 13
本郷民男
─ 王権に属した歳時 ─
〇 文明は飛鳥から
今回から、日本に入ります。美術史家の大橋一章氏は、「飛鳥の文明開化」という表現で、飛鳥寺の創建を称えました。仏教が日本へ伝来したのが『日本書紀』では552年ですが、『元興寺縁起』の538年が正しいとどこかで聞かれたでしょう。『元興寺縁起』は、この飛鳥寺の創建を伝える文献です。飛鳥寺は588年頃に発願され、百済から建築や金属加工の師匠を招き、609年頃に完成したと見られています。飛鳥のほぼ中央に、三棟の金堂、法隆寺の五重塔より少しこぶりな五重塔などが並び、中金堂には丈六の金銅仏が安坐していました。瓦も礎石も仏像もない国に、一足飛びで文明の精華が出現しました。
1981年に飛鳥寺西北の水落遺跡から、漏刻(水時計)の遺構が発見されました。『日本書紀』660年(斉明天皇6年)に、皇太子(後の天智天皇)が漏刻を作って人民に時を知らせたとあり、その遺構と判断されます。二十年ばかり前に唐の呂才が四段式の漏刻を考案し、その構造がわかっています。水落遺跡の遺構から四段式の漏刻を復元すると、見事に一致しました。水落遺跡を発掘した木下正史氏は、時刻を正確に測定して知らしめて人を服従させることは、天と人を支配する王権に不可欠なことであるとされています。
水落遺跡は単なる水時計ではなく、多くの建物や施設から構成されています。『日本書紀』には飛鳥寺西の槻の木の下で、種子島や蝦夷といった、遠方の使節をもてなしたといった記述が出てきます。槻は、ケヤキです。ここに、塔のように高い須弥山を築いた記録もあります。中大兄皇子等が蘇我本家を滅ぼした直後に、槻の木の下に豪族を集めて、服属を誓わせました。大友皇子と大海人皇子が争った壬申の乱では、大友側が槻の木の下に陣を構えましたが、大海人側が撃破しました。水落遺跡を含む飛鳥寺西方は、天地人を支配する重要な拠点でした。飛鳥寺は蘇我氏が建立しましたが、蘇我本家が滅んでからは、官寺となりました。飛鳥寺五重塔・漏刻・槻の木・須弥山は、人と天との接点でした。
〇 暦も飛鳥時代から
歳時記は暦によって運用されます。漏刻も、暦あっての時計です。553年(欽明14年)6月に、百済に対して暦博士などを交代させて欲しいと要請しました。翌年の2月に、暦博士固徳王保孫らが、派遣されて来ました。その前から輪番制で暦博士が来て、その時に暦を持って来てくれたはずです。602年(推古10年)には、百済僧の観勒が暦や天文地理などの本をもたらしたので、書生を選んでそれぞれの分野を学ばせました。これらから、暦は百済に依存し、日本人だけでは運用も覚束ない状況だったでしょう。『政治要略』には、小治田朝十二年の正月から暦日(暦)の使用を開始したとあります。推古11年に、小墾田宮へ移ったとあるので、小治田朝とは推古朝で、12年は604年です。飛鳥の宮殿はなかなか特定できないのですが、1987年にそれまで雷丘東方遺跡と呼ばれていた所から、「小治田宮」と書かれた墨書土器がたくさん出土して、場所の特定ができました。飛鳥寺がだいたい完成した頃に、ハードもソフトも基礎ができました。
暦は消耗品のため現物の最古は、水落遺跡のすぐ北の石上遺跡から出土した689年(持統3年)の木簡です。紙が貴重なので、初期の暦は木簡だったとみられます。紙の暦は奈良時代のものが、各地で発見されています。みな漆紙文書です。使用済みの暦を漆容器の蓋に再利用したのが、漆の保存力のおかげで残ったということです。