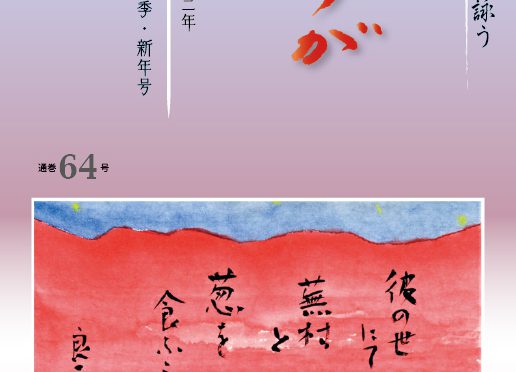素十俳句鑑賞 100句 (3)
蟇目良雨
(14)
ふるさとの喜雨の山王村役場
素十の故郷は茨城県北相馬郡山王村大字神住(現在は茨城県取手市藤代神住。平成17年3月28日合併による呼称変更による。巻末の資料参照)。小貝川が利根川に入り込もうとぐいと流れを曲げたあたりにある静かな農村である。 周囲を見渡すと小貝川の低い堤防とその上に筑波山が頭を出しているのが見える広々と開放感のある土地柄で、農家だった生家は平成9年頃まで萱葺き屋根であった。その後すぐ茅葺きは壊された。
生家のある神住から役場のあった山王まで歩いて十分ほど。多少の町屋が並びだして山王村役場跡に着く。今は山王公民館として使われている。ここには〈 ふるさとを同じうしたる秋天下 素十 〉句碑が据えられている。
掲句、喜雨の中の山王村役場であることよと言っているに過ぎないが、畳みかけるような心地よいリズムの中に故郷への賛辞が籠められていると思う。小貝川はよく氾濫した川であることを思えば、この喜雨の程よく降っている降りぶりに安らぎの気持が込められているといってもよい。
素十は山王村小学校を六年で卒業すると故郷を離れ長岡中学、一高、東京帝国大学と進み、学生時代に帰省してよく岡堰に遊んだりしたが故郷山王村へは住むことなく一医学徒として東京、新潟、奈良、相模原で生活して一生を終った。長岡中学へ進学した理由として、六年の時に校長排斥運動をして地元の中学校への推薦状が貰えなかったことが挙げられる。長岡には母ぶんの弟・毅がガス会社を経営し一人娘の婿にしたいという思惑もあったと言われる。
(15)
片栗の一つの花の花盛り
片栗の花はよく群生する。地下の球根を採掘して「カタクリ粉」を取る村人にとって見て楽しんで掘ってうれしい宝の山のようなものであったろう。 片栗は里山の日陰の斜面を好むようであるが、まだ枯れ山の空が木々の緑の葉で覆われる前の三、四月に差し込むわずかな日光を利用して地下の鱗茎を太らせて花を咲かせる宿命に起因するらしい。花を咲かせた後は、五月頃に葉も落とし翌年の三月まで十ヶ月の間は地中で球根のまま休眠する。この球根を掘り出して片栗粉を取るのである。片栗は種子が地中に入ってから八年目で開花するというから片栗粉として私達の口に入るまでに十年近くの歳月が経っていることになる。古名のかたかご傾籠に似て籠を傾けたようにして咲くところから「かたかご」とも言われる。
この句、片栗の花の群生もすばらしいものであるが、鉢植えの一つの花でさえよく見るとその花の作りの巧妙さに驚かされてつい口ずさんだものである。花盛りというのであるから六枚の花弁を思い切り上へ跳ね上げてあたかも乙女が舞っているように感じとったのかも知れない。薄日のなかに一瞬の春を謳歌している片栗の花への賛歌である。素十のやさしさを感じて余すところが無い。
(16)
尼さまの月の盃のせたる手
これこそ俳句の特質を活かしきった句作りであろう。「もの」を述べただけに過ぎない十七文字から漂う芳香。
尼さまがいて、お月見をしていて、手に酒の入った盃を持っている。その手はと見ると庵暮らしの作務で鍛えられたたくましさがありありと見える。ひと時の寛ぎに頂く酒。そして尼さまの至福の一瞬。竹林深き草庵に月光が射し日本人の理想郷が現れる。
「月の盃」という即物的表現が句を過不足なく完成させている。言葉を磨き上げた素十の努力を知るべきである。
盛唐の詩人王維に「竹里館」がある。
独 坐 幽 篁 裏 独り幽篁のうち裏に坐し
弾 琴 復 長 嘯 弾琴 また 長嘯
深 林 人 不 知 深林 人知らず
名 月 来 相 照 名月 来りて相照らす
これは中国の隠者の理想郷。王維は寂しさの余り音を欲しがっているようにも読みとれる。月と盃は日本人の理想郷。月光と一杯の酒があれば足りる。