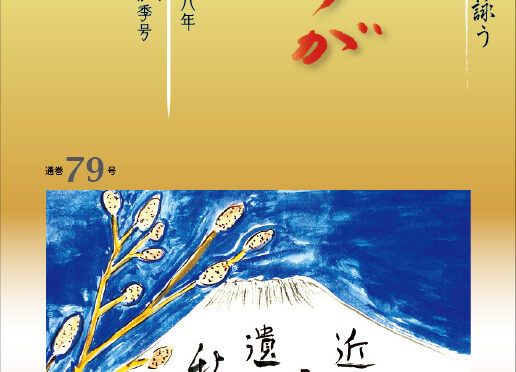韓国俳句話あれこれ 24
本郷民男
▲ 句集『朝鮮』
京城で昭和5年に、『朝鮮』という句集が出ました。笠神志都延の編で、京城日報社の発行です。名の読みが良くわかりませんが、「しづのぶ」のようです。志都延は1891年に岩手県の水沢で生まれました。東京高等商業(今の一橋大学)を卒業し、更に中央大学法科を卒業しました。読売新聞などを経て、京城日報の主筆・編集局長などを務めました。京城日報は文芸欄が充実していました。
ところがこの少し後に京城日報を辞めて、以後は満洲の新聞人として活躍しました。最後に名が見える記録は、鹿野久雄「ソヴェト抑留記」です。鹿野は昭和21年にカザフスタンの首都アルマアタの収容所に送られ、砕石の作業をしました。インテリばかり集められたので、句会を開きました。その中に笠神句山の名があります。俳人句山(志都延)は秋まで健在でした。たぶんアルマアタの土になったのでしょう。
実際の編集は庄司鶴仙(清次郎)が行いました。鶴仙は1892年に宮城県に生まれて、新聞記者をしていました。1921年の「新聞年鑑」に、京城日報の編輯部員として庄司清次郎の名があるので、志都延の命を受けて句集を編集したのでしょう。臼田亞浪の「石楠」に属し、京城盟楠會を創立しました。京城日報の俳壇の選者を臼田亞浪が務めたこともあり、適任でした。
ただし、『朝鮮』では旧派・「ホトトギス」・「石楠」といった枠にとらわれず、幅広く句を収集しました。中にはある程度名をなした俳人も見られますが、辺境の無名の作者が多いです。
ところがこの少し後に京城日報を辞めて、以後は満洲の新聞人として活躍しました。最後に名が見える記録は、鹿野久雄「ソヴェト抑留記」です。鹿野は昭和21年にカザフスタンの首都アルマアタの収容所に送られ、砕石の作業をしました。インテリばかり集められたので、句会を開きました。その中に笠神句山の名があります。俳人句山(志都延)は秋まで健在でした。たぶんアルマアタの土になったのでしょう。
実際の編集は庄司鶴仙(清次郎)が行いました。鶴仙は1892年に宮城県に生まれて、新聞記者をしていました。1921年の「新聞年鑑」に、京城日報の編輯部員として庄司清次郎の名があるので、志都延の命を受けて句集を編集したのでしょう。臼田亞浪の「石楠」に属し、京城盟楠會を創立しました。京城日報の俳壇の選者を臼田亞浪が務めたこともあり、適任でした。
ただし、『朝鮮』では旧派・「ホトトギス」・「石楠」といった枠にとらわれず、幅広く句を収集しました。中にはある程度名をなした俳人も見られますが、辺境の無名の作者が多いです。
▲ 新年の句
戎克皆支那正月の濱にあり 奥村梅園
骨正月よき碁敵の来りけり 古藤孫六
禮砲の響き渡るや初御空 □田□原光
泊船の注連を渡れる日色かな 磯貝金鶴城
骨正月よき碁敵の来りけり 古藤孫六
禮砲の響き渡るや初御空 □田□原光
泊船の注連を渡れる日色かな 磯貝金鶴城
戎克は英語のjunkに充てた語です。作者は中国の大連の人です。支那正月とあるので、旧暦の正月です。次の「骨正月」は関西の二十日正月です。外地に移住するのは、たいてい西日本の人たちでした。禮砲は時代を感じさせます。作者の名は、活字がつぶれて読めません。泊船つまり停泊している船にも、日本式に注連縄を飾りました。なお、芭蕉は自分の庵を、泊船堂とも呼んでいました。
黎明の中の鳥居や初詣 一ノ瀬米村
蓬莱や王者顔なる海老の髭 三瀬みのる
屠蘇くむや馴れて住みよく高麗の國 稲葉一蝶
蓬莱や王者顔なる海老の髭 三瀬みのる
屠蘇くむや馴れて住みよく高麗の國 稲葉一蝶
羽子抱いてほほ笑む吾子の夢路かな 梶原盆地
神社を建て、日本の風習をそのまま持ち込んだ正月の風習が並んでいます。
(つづきは本誌をご覧ください。)