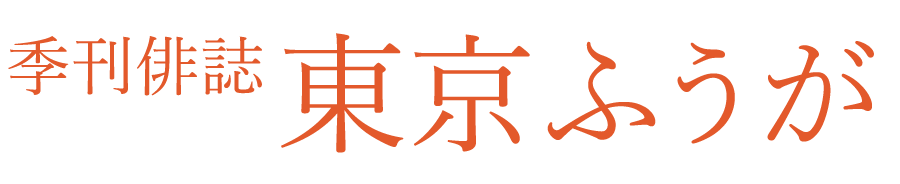寄り道 高野素十論
その19
蟇目良雨
飴山實の「自然の真と文芸上の真」論争不毛論
寄り道高野素十論(その18)の結論に私は次のように述べた。
「西洋医学を学び、秋櫻子と同様に西洋の芸術にも詳しい筈のみづほも素十も今夜も、虚子のこの東洋的な味わいの前には脱帽せざるを得なかったのが当時の現状である。勿論、秋櫻子も同じ道をたどってきたのであるから虚子の句作りを相当評価していたのだが、敢えて不毛の論争を挑んだのは冒頭に述べたように「目くらましの論争」を虚子側と交すことになったのだと私はいよいよ意を深くした。」と。
最近、「自然の真と文芸上の真」論争が不毛であるばかりか、その後の俳句の本質を誤った方向に導いたという厳しい意見があることを知った。それをしばらく検討してみる事にしよう。
「角川俳句」昭和55年1月号に掲載された、
<新春座談会>今日の俳句、明日の俳句 で
飴山實、宇佐美魚目、川崎展宏の三氏の鼎談で、司会は明記されていないが編集長鈴木豊一である。ここに全文掲載できないが順序を追って話を聞いてみる。
三人は昭和元年前後に生れた者同士。虚子門の宇佐美魚目と加藤楸邨門の川崎展宏、上記二人は師と呼ぶが、飴山實に師は無く、沢木欣一、金子兜太、安東次男、原子公平を兄貴として兄事したと言っている。
そして終戦になった時代の空気を「風景が透明になった」「空気が澄んでいた」と口を揃えて言う。飴山實が出征しなかったのは理科系学生だったせいで、宇佐美は昭和20年4月から8月15日まで内地を砲弾が一発もない大隊砲の兵科に属し金沢、千葉、茨城の砂浜を彷徨した。川崎は一番若いので学徒動員はあったのだろうがここでは触れていない。そういう年代の三人である。
鼎談の開かれた少し前に川崎展宏が書いた『わが愛する俳人』の中の高浜虚子論が素晴らしいと鼎談の話題になったが、虚子の身近にいる清崎敏郎の細かな観察には負けたと展宏が言葉を続ける。その証拠として
「丸ビルへ通う横須賀線の車中で、鎌倉を出はずれると、かならずシートの上で袴を脱ぎだす虚子。用便の為です。そんなこと高木晴子さんが書いていられたの、あれ評判になりましたけれど、虚子を目の前で見るようだ。」と身近な人の観察を褒めてさらに展宏は言葉を継ぐ、
「それから、ぼくは花鳥諷詠というのは、これは解ります、傲慢な意味じゃなくて、つまり、自分自身の力量というか、自分自身の身の幅と身の丈なりにね、花鳥諷詠は感じ取ったと思いますよ。」と虚子の花鳥諷詠を展宏が認めたことを受けて飴山實が話の穂を継ぎ始める。ここは重要なので飴山の言葉を誌上掲載してみよう。
飴山
「虚子についてはあなた自身が感じた花鳥諷詠、あるいは高木晴子さんの身近な文章、こういうのがいままでなさ過ぎたんで、みんな抽象論だったみたいね。花鳥諷詠にしても虚子の俳句にしても、虚子というものはこんなものだという観念が先にあってね、それが続いておったから、具体的なものは何もなかったという感じがせんでもない。だから一人一人の中の虚子が出てこないと本当の虚子が出てこない。たまたま虚子の場合は、秋櫻子以来の新興俳句が出て、虚子を棚上げしたような時代が長かったから、観念的な把握しかなかったといってもいいんじゃないか。」
飴山
「(前略)だから大正初期の蛇笏、普羅、石鼎、鬼城というような人の時代、それから大正期から昭和初めのいわゆる昭和俳句の台頭してくるところ、秋櫻子、誓子、草城とかこれは皆さんおっしゃるようなピークですよ。で、さっきの変化が出てくるのは、やっぱり秋櫻子が一人前になってそのうちに虚子、「ホトトギス」から離れますね。あの辺から昭和俳句、非常に絢爛たる昭和俳句が始まったといわれるところですけどもね。」
飴山
「俳句史と俳壇史を皆さんチャンポンにしている。俳句の歴史と俳壇の歴史はまったく別なものだと区別して考える必要があると思うんですよ。「自然の真と文芸上の真」という秋櫻子の文章で、秋櫻子が虚子から離れたのは俳句史の上の大事件と考えて、そこから後の昭和俳句に入って今日までつながっておるという一般の見方だけどね。あの秋櫻子と虚子の当時のいきさつを見ると、俳句の上の問題じゃなくて、単なる喧嘩なんだ。俳壇的な事件であって、俳句的な事件ではないと、ぼくは思う。(後略)」
川崎
「俳壇の事件であって俳句史の事件ではないということは、それは虚子と秋櫻子とは純俳句的な観点から見た場合には異質でないと・・・。」
飴山
「いやたしかに異質なんですけれどもね、普通には秋櫻子以降の昭和俳句は固陋な「ホトトギス」の俳句から離れて、飛翔して、そして進歩してきたのだいうようなつかまえ方があるけれども、そうじゃなくて、むしろあすこから俳句は本筋から離れてヘボ筋に入ってきたと見るわけです。」
川崎
「ヘボ筋というのは聞かなきゃいけないな。」
飴山
「ヘボ筋というのは、俳句の性質にかかわることなんだけれども、秋櫻子は窪田空穂の短歌、それから誓子はその秋櫻子に接触し、かつ啄木とか、齋藤茂吉の歌を読んでますね。そういうように昭和俳句のスタートは、短歌を研究した、短歌に関心のある人達から出発している。万葉語をあの頃使っていますが、これはまあ現象だけですけどね。