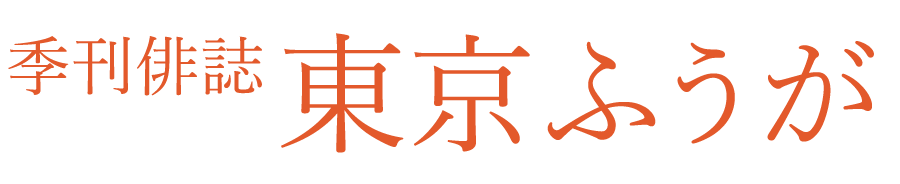素十俳句鑑賞 百句 (9)
蟇目良雨
(61)
冬青の花こぼるゝ日なり更衣
大正15年7月 虚
冬青の花(黐の花)は葉の常緑が好まれて庭木に植えられている。花は目立たたないし、赤や灰色の実も小鳥たちの食べ物になる程度で人様をよろこばすものではない。四季を通して緑を湛えていることが好まれるのであろう。気が付けば花を咲かせ、いつの間にか実を付けていることに気が付く自己主張の無さが庭木として好まれるのかも知れない。更衣の季節になりふと庭を見遣ると冬青の花が零れ続けている。ああ、こんな季節になっていたのだと作者は時の移ろいを静かに受け入れているのである。詩情に溢れる一句になった。
(62)
打水や萩より落ちし子かまきり
大正15年9月 虚
打水が萩の葉に止まっていた子蟷螂を落としてしまったという内容ながら、打水の水量や落ちた子蟷螂を取り囲んで何かお喋りし合っている声までが聞えて来そうである。通路に面した萩の辺りへ柄杓でさっと水を打ち、その僅かな水量に流されて子蟷螂が落ちる。それを目ざとく見つけて「あら、子供のかまきりが落ちてしまったわ」「どれどれ。ああ本当だ」「大丈夫かしら」「この位の水だから大したことは無いよ」「ああ、よかった」若い夫婦の会話が聞こえて来そうである。
(63)
露けさや月のうつれる革蒲団
大正15年9月 虚
革蒲団は肌触りが涼を呼ぶということから夏に用いられる座布団のことである。羊や山羊のなめし皮が用いられるのでワックスで手入れすればツルツルに磨かれたことだろう。縁側で涼を取っていると、人の立った後の革蒲団に月が映って見える。うすぼんやりした月の影をみて夜の露けさを感じたのである。革蒲団などは高級品である。素十がこの頃住んでいたのは叔父(母の弟)の家で、叔父は長岡で天然ガス会社を経営し文京区音羽に豪邸を建てて、素十もそこに居候をしていた。この家での作品と思いたい。