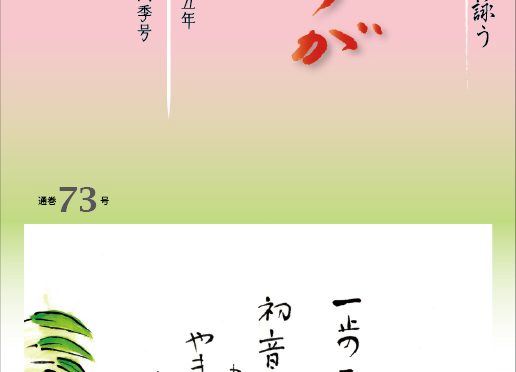素十俳句鑑賞 百句 (12)
蟇目良雨
(91)
もちの葉の落ちたる土にうらがへる
昭和4年
ホトトギス誌で四Sと呼ばれて客観写生を突き進む素十の目に映ったものは何でも俳句になる。黐の木の葉が落ちて土の上で天地を変えたことが不思議に見えたところに素十の観察が深まる。たまたま裏返ったというより大方が裏返るのは、黐の葉の特徴がそうさせるのだろうと思ったのだろう。黐の葉は中心から折り畳みが出来そうなくらい丸まっている。このせいで地に着いてから裏返り易いという結論を得て一句が成った。「だからどうした」と言う声がありそうだが、素十には自然の摂理に感動する力の方が大きいのである。
落葉が季語である。
落葉が季語である。
(92)
玉解いて即ち高き芭蕉かな
昭和26年
素十は前年に新潟大学医学部長兼新潟医科大学学長を退き俳句一筋の生活に入ったが、この年はホトトギス雑詠選が虚子から年尾に変わった時期に当たる。虚子選を受けられなくなった素十は、当然複雑な思いを抱いたに違いない。虚子との吟行会で年尾と一緒になったこともあり、年尾の技量は知り抜いていた。そんな中での作品である。
未だ葉を巻き付けている棒のような芭蕉が、葉を広げ始めると見違えるように高く見える。素十の心の中に独り立ちをする感慨が生まれた瞬間であった。
(93)
麥を打つ頃あり母はなつかしき
昭和14年