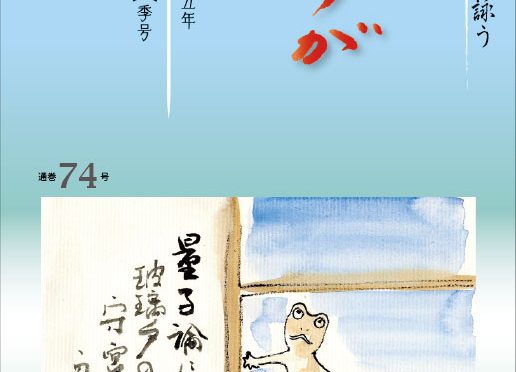コラム はいかい漫遊漫歩 『春耕』より
松谷富彦
186
歌舞伎役者と俳句(上)
台風の去って玄界灘の月 初代・中村吉右衛門
〈 台風一過。というと、たいていの人は白昼の青空をイメージするのに、あえて夜の空を詠んでみせたところがニクい。おぬし、できるな。それも、普段でも波の荒いことで知られる玄界灘だ。台風が去ったとはいっても、真っ暗な海はさぞかし大荒れだろう。その空にぽっかりと上がった煌々たる月影。さながら芝居の書割りのごとくに鮮明で、しかるがゆえに壮絶にして悲愴な情景と写る。句に、嫌みはない。〉と『増殖する俳句歳時記』で、詩人・俳人の清水哲男が鑑賞した一句。
詩の仲間、八木忠栄も同歳時記で〈 (玄界灘は)明治三十八年(1905)には東郷平八郎率いる連合艦隊が、ロシアのバルチック艦隊を迎え撃った、知る人ぞ知る日本海海戦の激戦地でもある。海戦当時、吉右衛門は十九歳。何ごともなかったかのような月に、日本海海戦の記憶を蘇らせ重ねているのかもしれない。〉と書く。
初代・中村吉右衛門は、明治十九年(1886)東京浅草生まれで、屋号は播磨屋、俳号(俳名)は秀山。六十五歳で文化勲章を受章、三年後の昭和二十九年(1954)に没した。
遺した『吉右衛門句集』の「あとがき」で、俳句を本格的に学ぶきっかけは、狂言「松浦の太鼓」の主人公、松浦鎮信が俳句を嗜む殿様で、役作りのために思い立ったと記している。四十代の昭和初年に高浜虚子に師事し、「ホトトギス」の同人にもなり、亡くなるまで詠句を続けた。
歌舞伎役者は、元々俳名を持ち、俳句を嗜み、名代披露の際には俳句を書いた扇子を配る仕来たりがあると、虚子は記している。〈 虚子は(『吉右衛門句集』の)序文で、吉右衛門の句は有りの儘を序した句に見えるが、それでいて、その奥に深い味が潜んでいる。といい、神仏に対して厚い信仰、家族門弟への深い愛情、世の中に対してつつましく謙虚な心持が出ている、と的確に評している。〉と俳句評論の坂口昌弘は、自著『文人たちの俳句』(本阿弥書店刊)で書く。
浅草寺右隣の浅草神社境内には、久保田万太郎らの句碑と並んで左記の吉右衛門句碑がある。
女房も同じ氏子や除夜詣 吉右衛門
吉右衛門の修善寺の初句碑には、次の詠句が刻まれている。
鶯の鳴くがままなるわらび狩
この句碑が建ったとき、吉右衛門が喜びを素直に詠んだ句を二つ。
夏わらびとつて来てまた句碑に立つ
我句碑を人に問はれて梅の花
俳句と弓道を趣味とした吉右衛門の一句を最後に引く。
炉びらきに弓も引くなり句も作る