「墨痕三滴」佳句短評
蟇目良雨による俳句鑑賞。(お茶の水俳句会会報396号以降)
俳句鑑賞「墨痕三滴」
高木良多、蟇目良雨による俳句鑑賞。(お茶の水俳句会会報395号まで)
蟇目良雨による俳句鑑賞。(お茶の水俳句会会報396号以降)
高木良多、蟇目良雨による俳句鑑賞。(お茶の水俳句会会報395号まで)
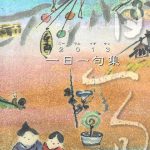 – 本書の特徴 –
– 本書の特徴 –
・2012年の世相を強化
・判りやすい俳句を一日一句
・季節をきりとる愛らしい挿絵
春耕叢書 平26ー1
頒 価 1500円
2014年12月5日 印刷
2014年12月26日 発行
著 者 蟇目良雨
発行所 春耕俳句会
印刷所 共信印刷
挿 絵 蟇目良雨
ブックデザイン 菫花舎

春耕叢書 平25ー2
頒 価 1500円
発 行 2013年12月9日
著 者 高木良多
発行所 春耕俳句会

– 本書の特徴 –
・2012年の世相を強化
・判りやすい俳句を一日一句
・季節をきりとる愛らしい挿絵
春耕叢書 平25ー1
頒 価 1500円
2013年10月9日 印刷
2013年10月31日 発行
著 者 蟇目良雨
発行所 春耕俳句会
印刷所 共信印刷
挿 絵 蟇目良雨
ブックデザイン ワタリマミ
どんな貧しい家でも門松は門の内か外に飾られてあるのが普通の家であるが、この句の門松は硝子戸の内側に飾られてある。大きなビルの立派な硝子戸の内側なのであろう。丸の内なればである。その意外性が面白い現代俳句となっている。

– 本書の特徴 –
・2011年の日々の出来事をメモ
・判りやすい俳句を一日一句
・蕪村の「奥の細道」画巻の模写を挿絵に
春耕叢書 平24ー1
頒 価 1500円
2012年7月18日 印刷
2012年8月18日 発行
著 者 蟇目良雨
発行所 春耕俳句会
印刷所 共信印刷
挿 絵 蟇目良雨
ブックデザイン ワタリマミ

– 三大特徴 –
昨年『2009一日一句集』を出したところ「また来年もやるのでしょう」というお言葉を何人かの方から頂戴した。拙著に対する感想の言葉に困りお世辞に発せられた言葉であることは判りつつも日記帳に出来事と一日一句だけは書き溜めていたのであった。
さて、2010年は記録的に暑い夏を日本人は経験した。この暑さの中を吾が師・皆川盤水先生は食道癌を身の内に養いながら療養されておられた。食道癌であったことは死後にご家族から知らされたのであるから、この暑さの峠を越えれば先生は本復することを信じていた。
この忘れ難き年を私の体内において風化させないためにも『2010一日一句集』を刊行しなければならないように思った。
春耕叢書 平23ー1
頒 価 1500円
2011年8月18日 印刷
2011年8月29日 発行
著 者 蟇目良雨
発行所 春耕俳句会
印刷所 共信印刷
挿 絵 蟇目良雨
ブックデザイン ワタリマミ

シイサアは、沖縄県などにみられる伝説の獣の像。建物の門や屋根、村落の高台などに据え付けられ、家や人や村に災いをもたらす悪霊を追い払う魔除けということである。獅子が訛ってシイサアとなったと言われるがこの句の手柄は屋根獅子と書いてシイサアと読ませたことだろう。空にもっとも近い屋根獅子が鰯雲に近づくように膝を乗り出しているように見えたと表現したことで俄然面白くなってきた。こうした遊び心が句を楽しくさせてくれるのである。写生句であるが「膝をのり出す」と見たところに作者の俳諧の主観がこめられている。
過日、神保町の古書店で氏の著書『海の旅 篠原鳳作遠景』を買って読んだが<しんしんと肺碧きまで海の旅 鳳作>を代表句としてわずか三十歳で死んだ篠原鳳作の短き波乱に富んだ一生を迫真の筆致で描いていたことに驚いたことを思い出した。
菜種を採ったあとの菜種殻はよく燃えるので松明の穂先に使われ火祭や左義長に欠かせないものである。また柔らかで且つしなやかなために箒にも使うことがある。この菜種殻の箒は蛍狩にも使われるのでその柔らかさが想像できるだろう。
一方、「うはなり打ち」とは中世にあった風習で、離縁された先妻が後妻(うわなり)のところへいじめに行くことを言う。別れてひと月もたたない内に再婚してしまった前夫への仕返しなのだがそのとばっちりを後妻が受けるという図式。
予告して押しかけるのであるが女ばかりで行くにしても木刀や竹刀などを持ってゆくので襲われた後妻の方は驚いたことであろう。作者は木刀や竹刀の代わりにこの菜種殻を用いてあげたらいいのにとつぶやいているのである。
「菜種殻」と「うはなり打ち」を結びつけて句が俄然面白くなったが、歴史ものに素材をとって蕪村的世界が描けたのではないだろうか。
葛の葉が秋の季語になっているのは「葛の葉」が風に翻って白い裏を見せる「裏見」が「恨み」に転じて秋のあわれさ と結びついたからである。
葛の葉のうらみ貌なる細雨(こさめ)かな 蕪村
など季語の内容むき出しの使い方である。
掲句は真葛原の発するざわめきの様子を「二ごころある」ざわめきと看做したところが非凡である。凡人には決して見えてこない把握の仕方であると感心した。見えないものを見るように努めるのが詩人の仕事。