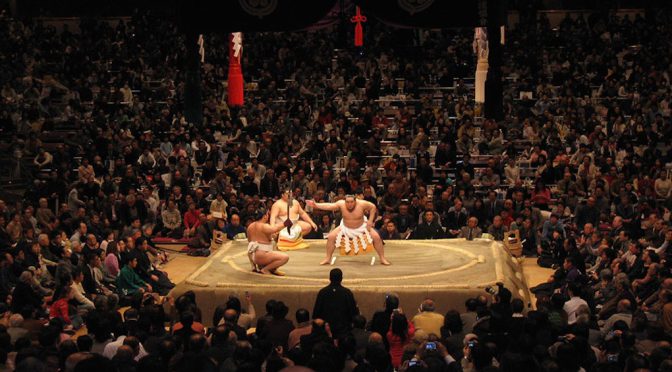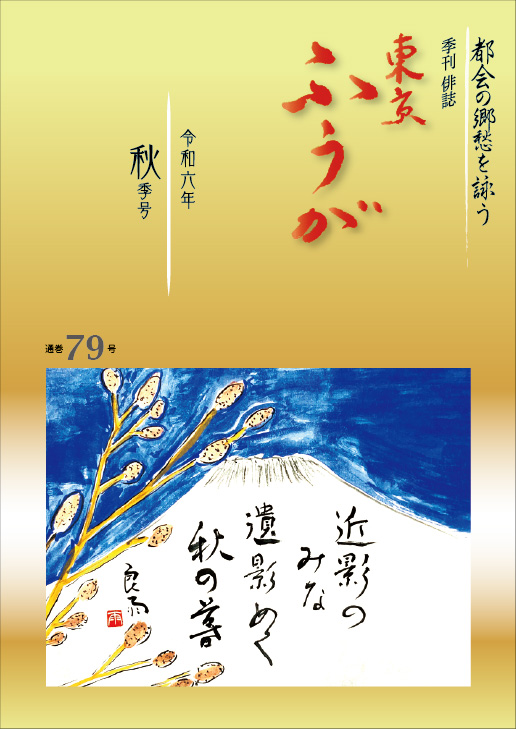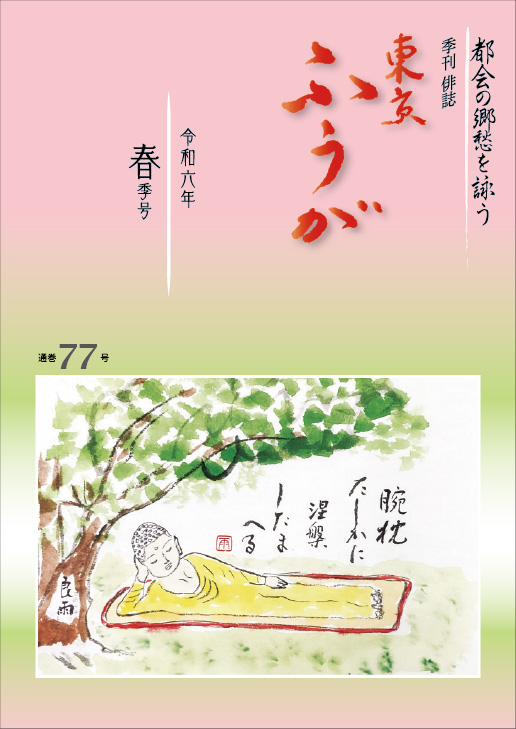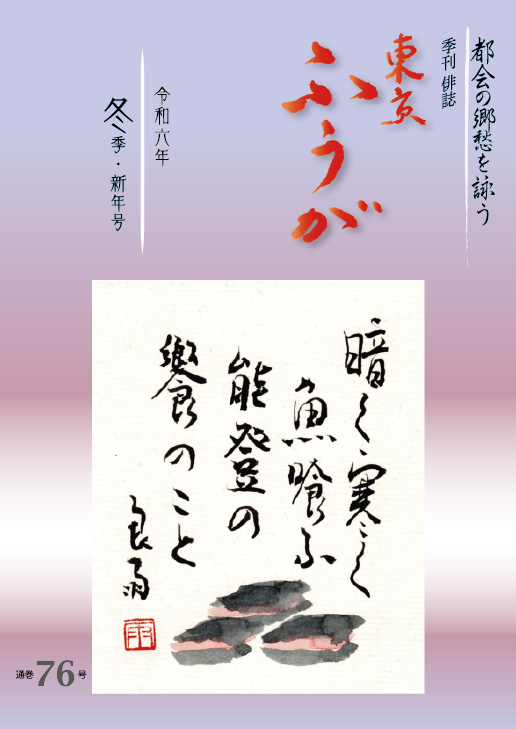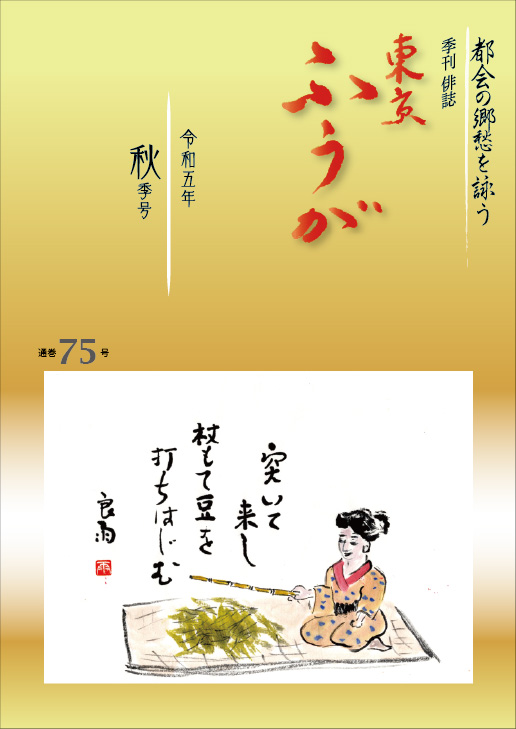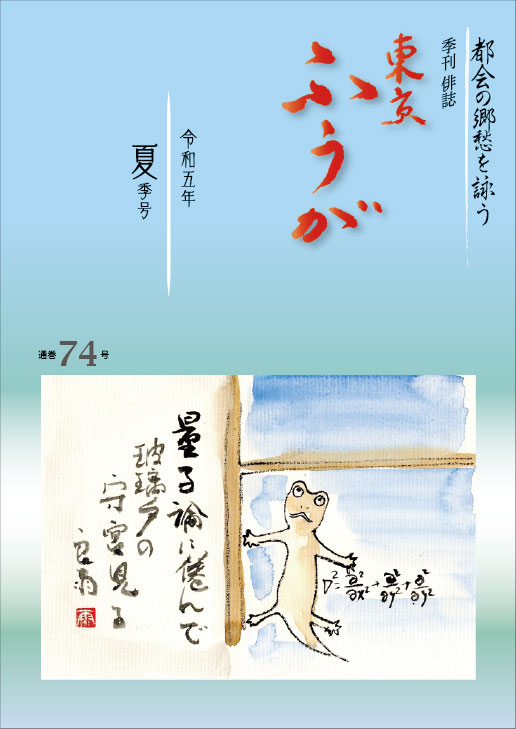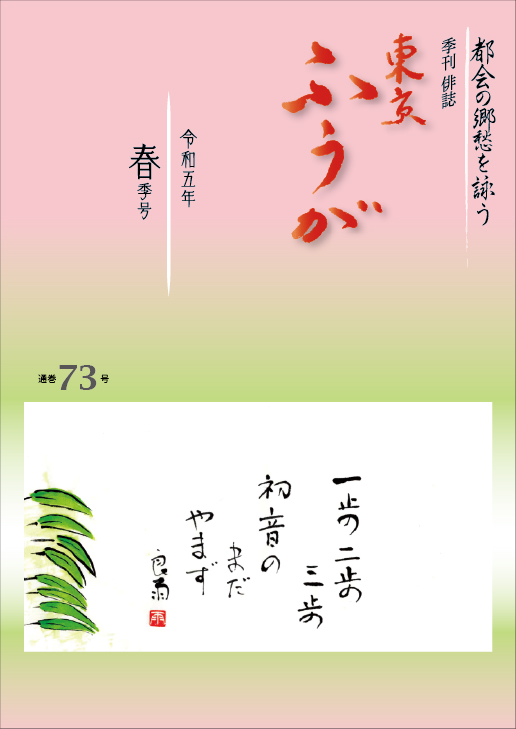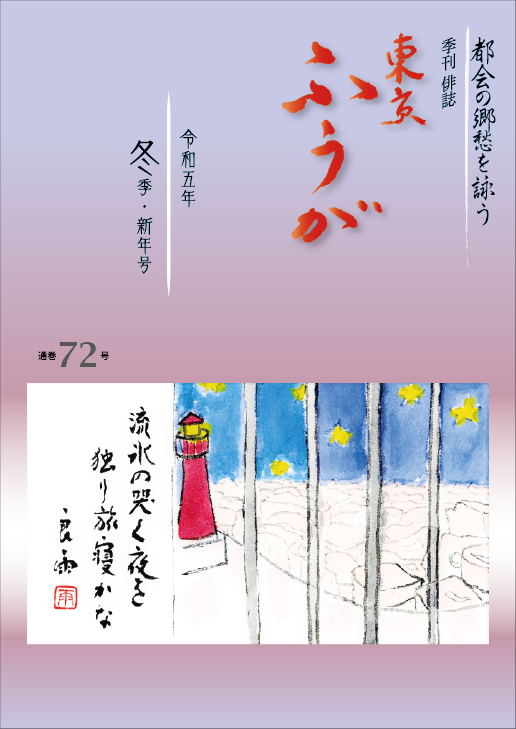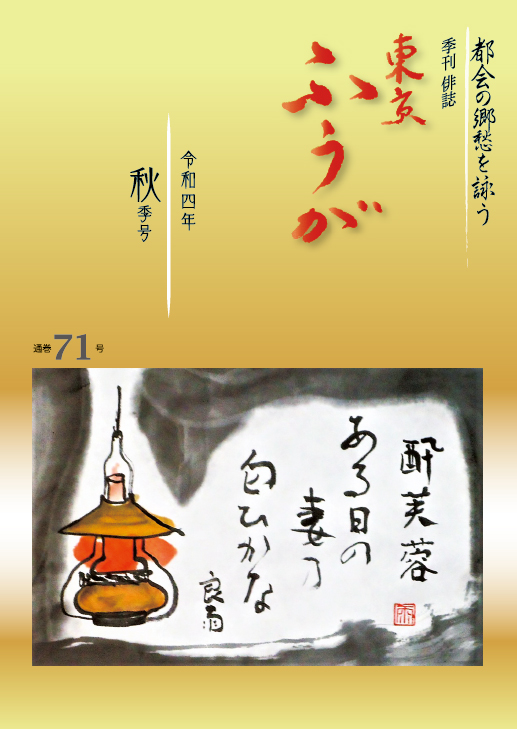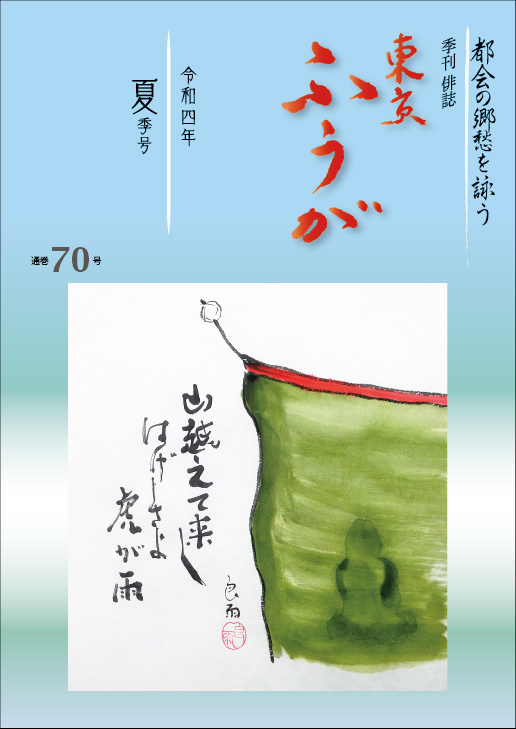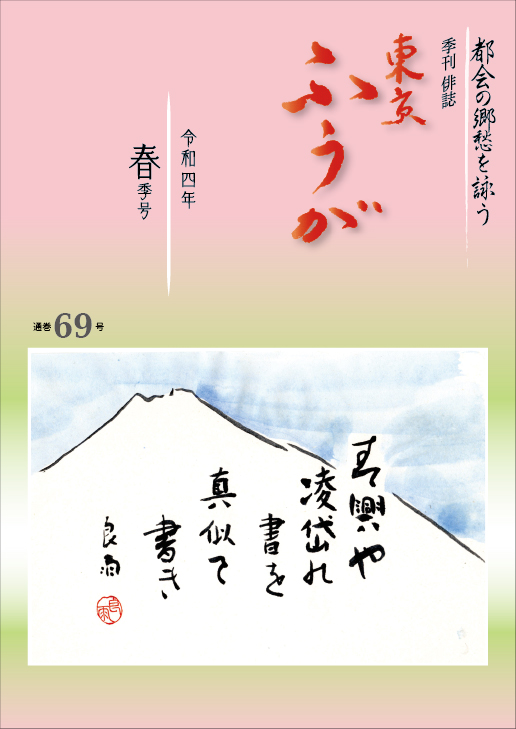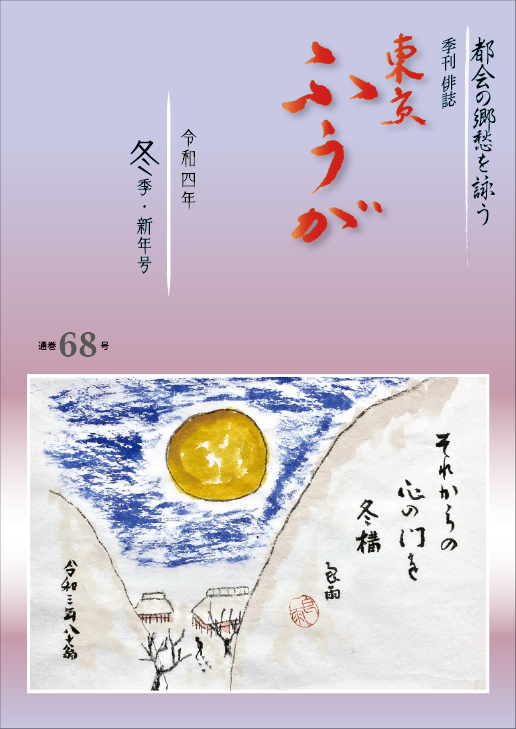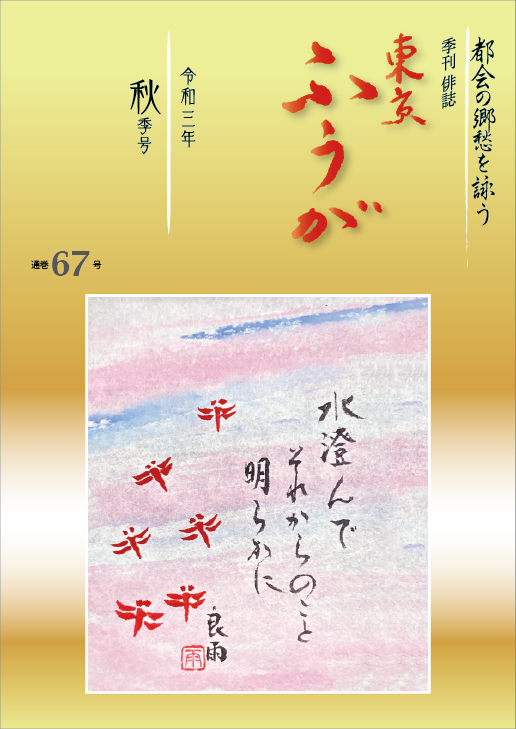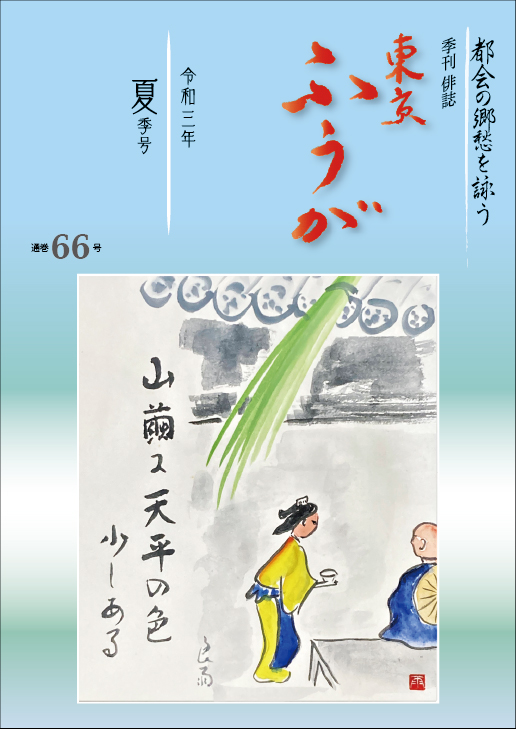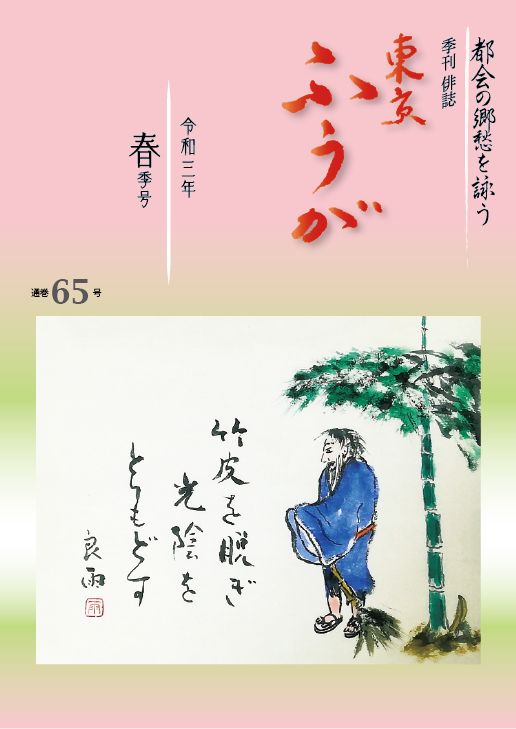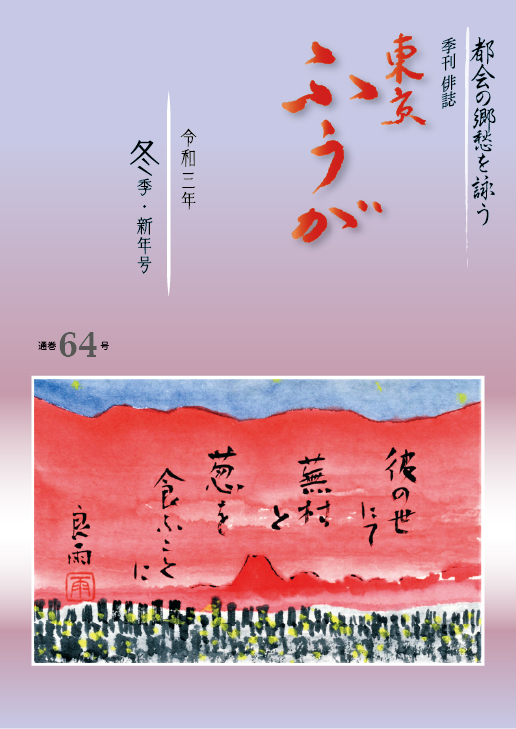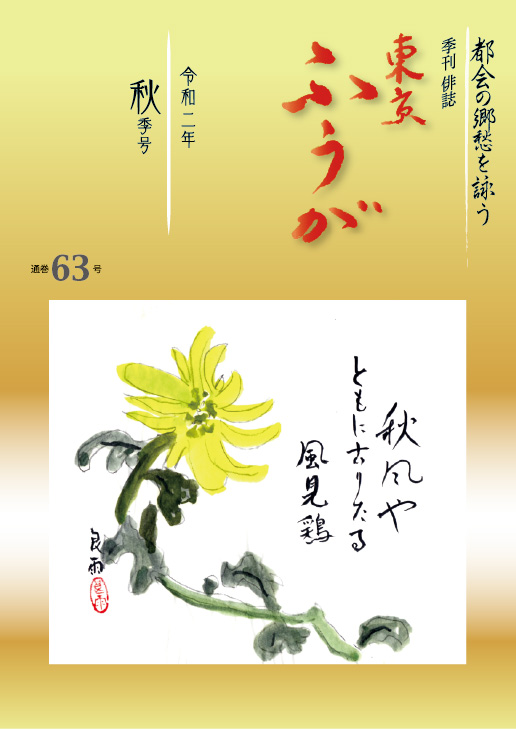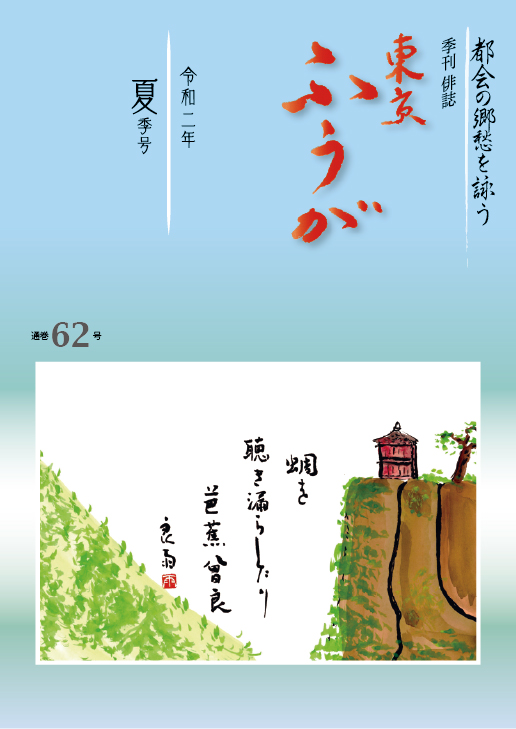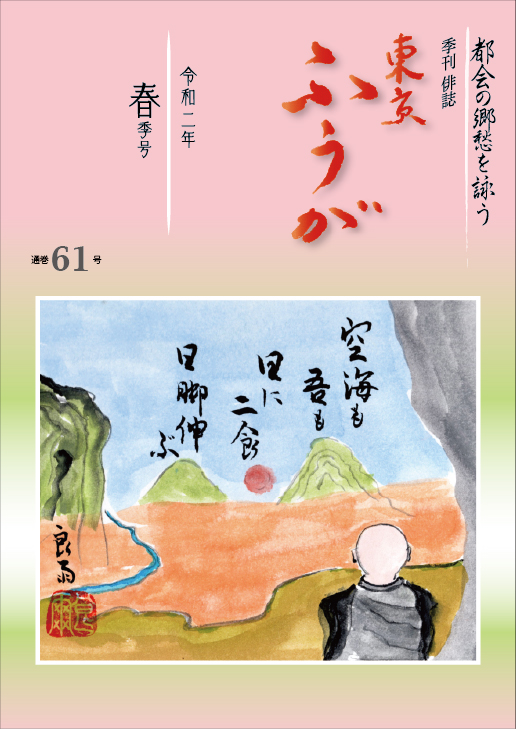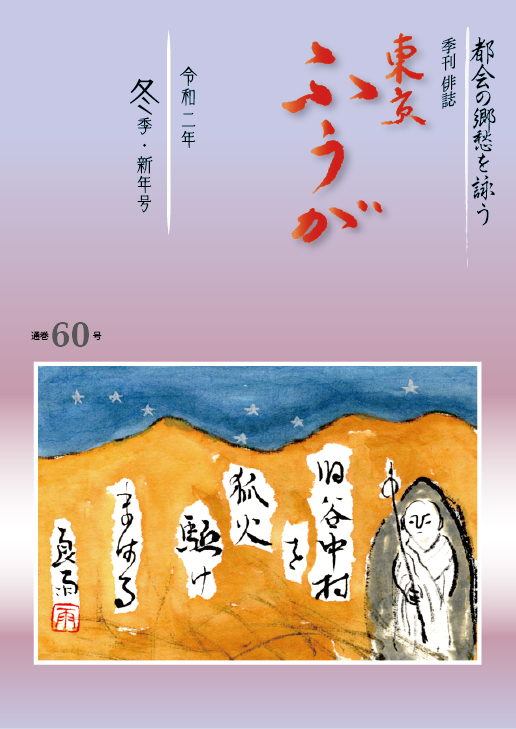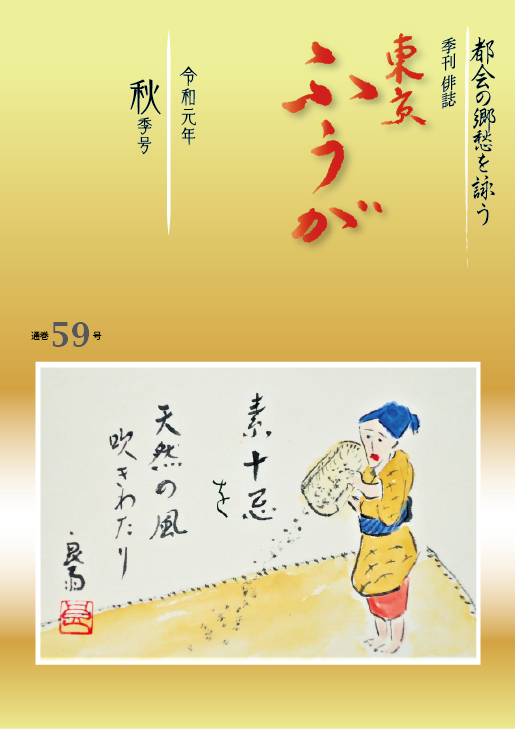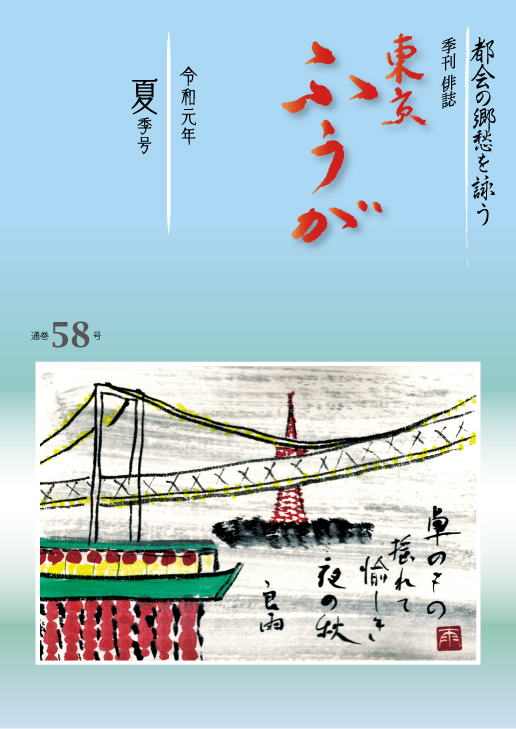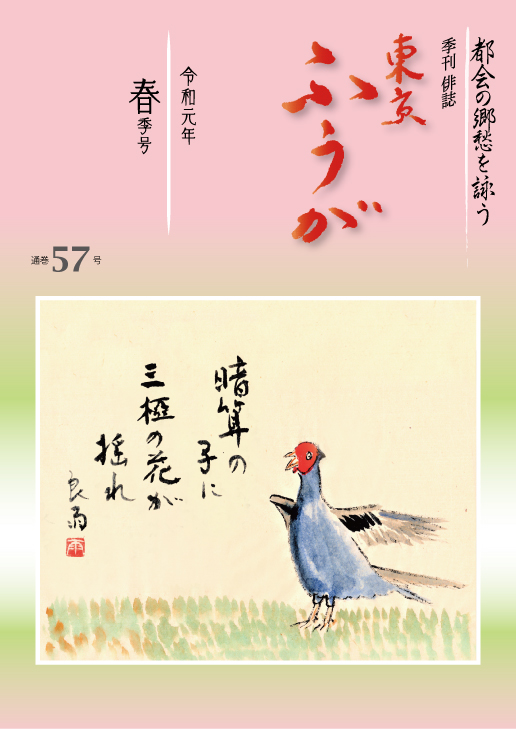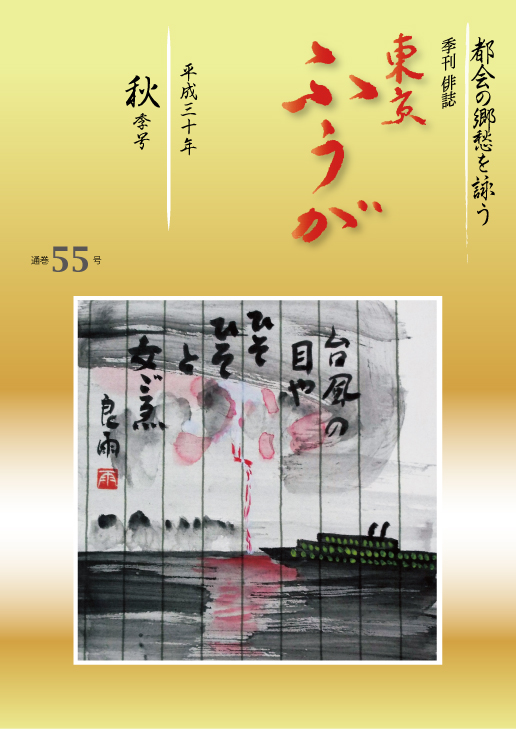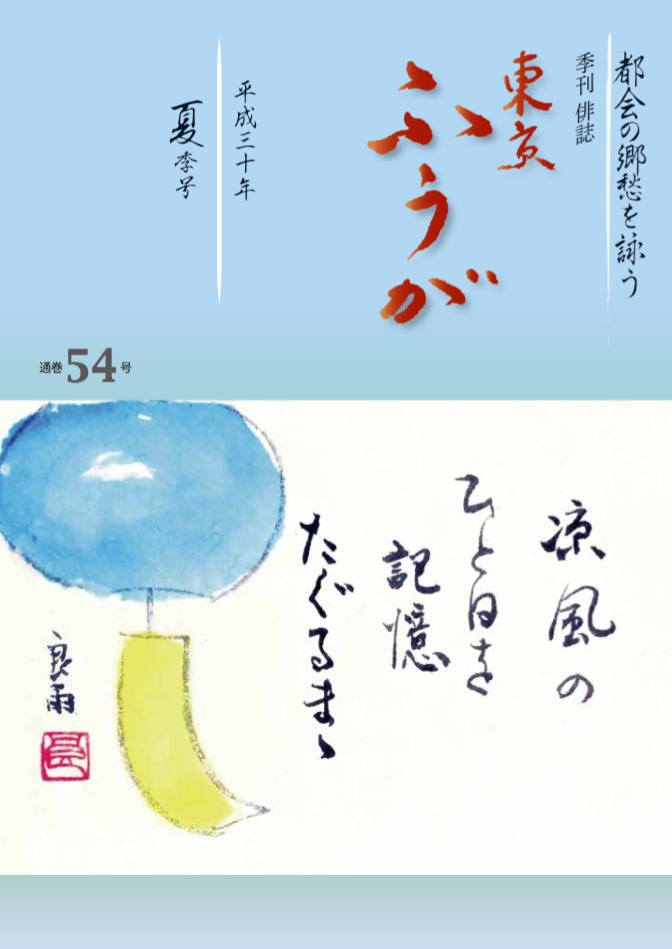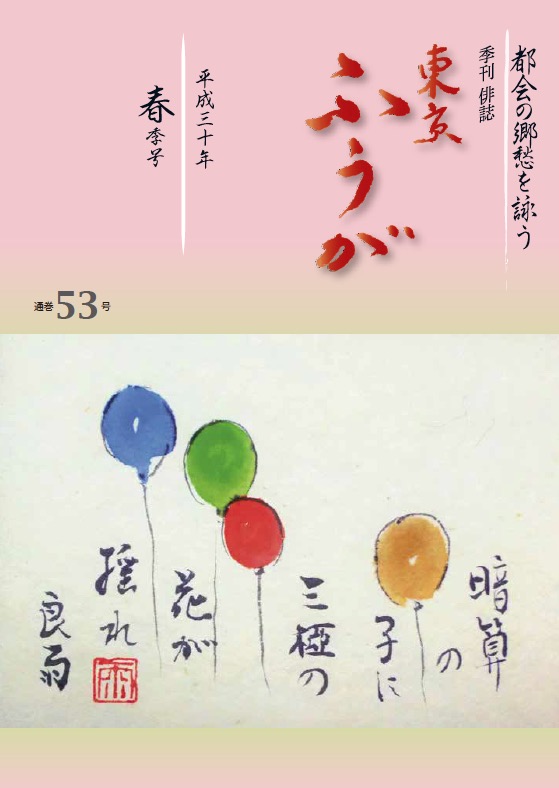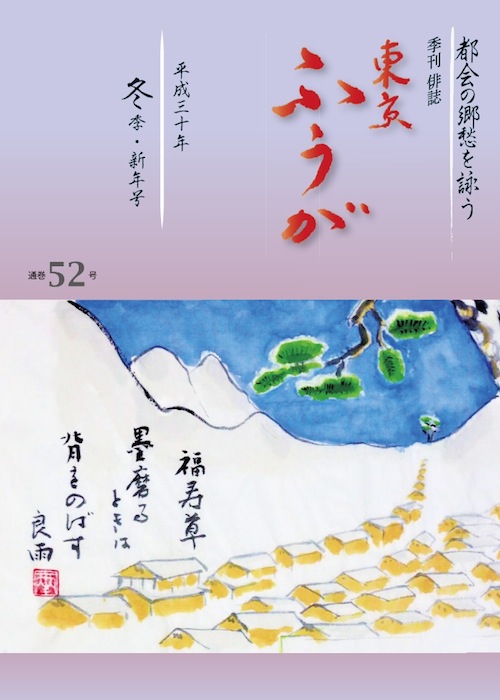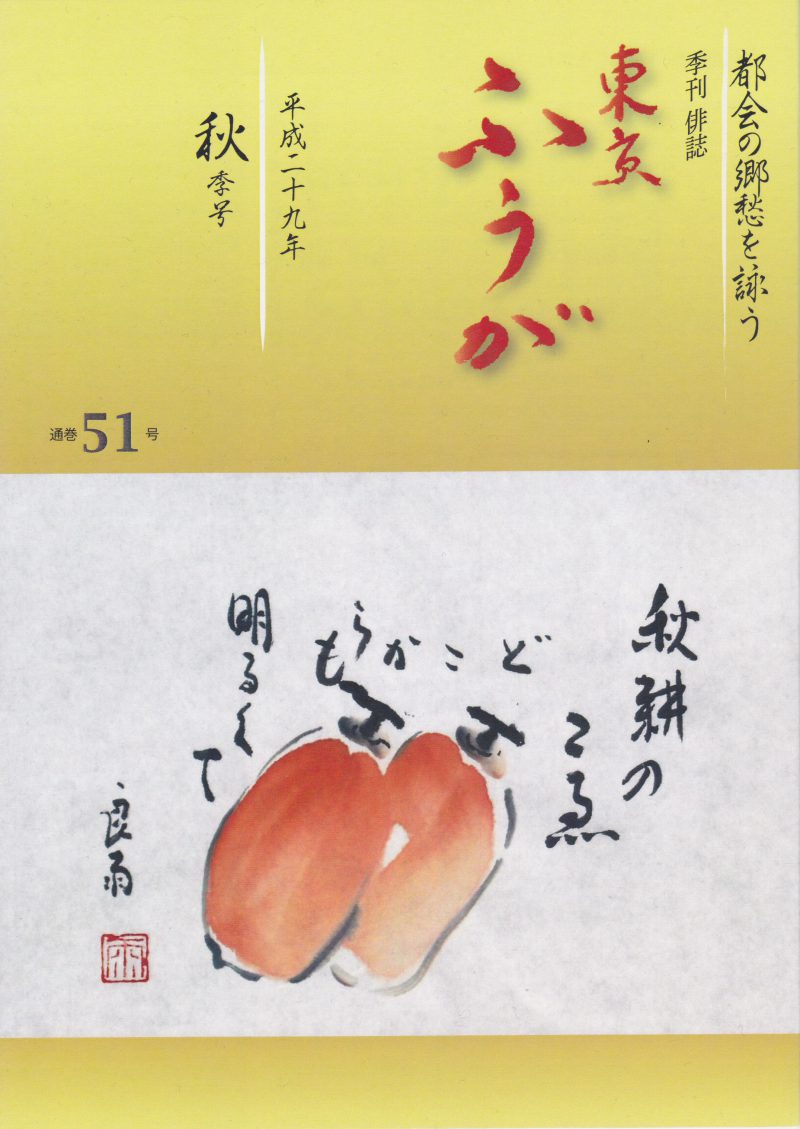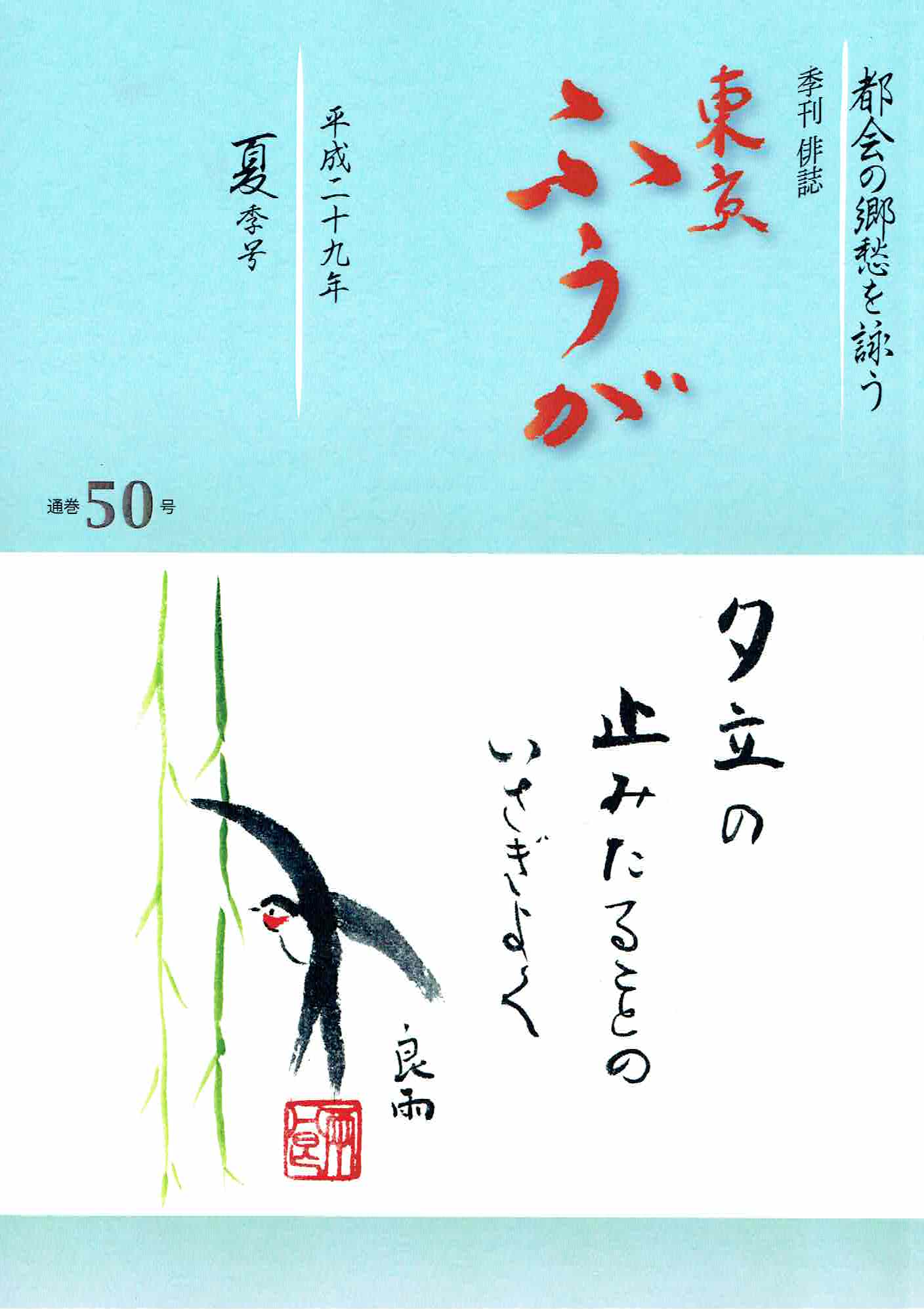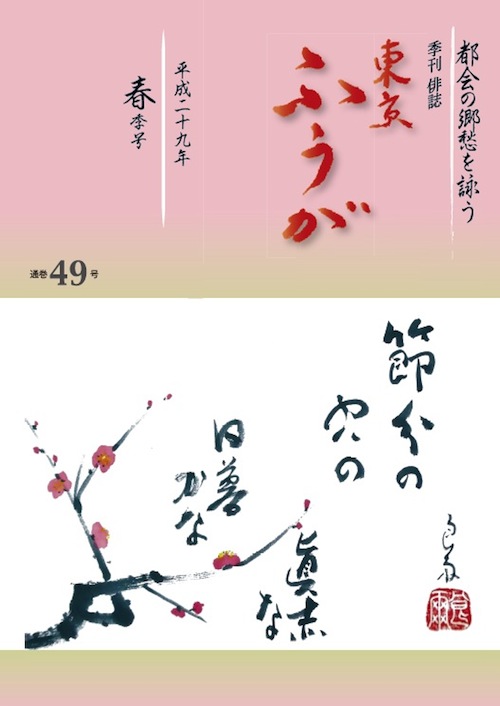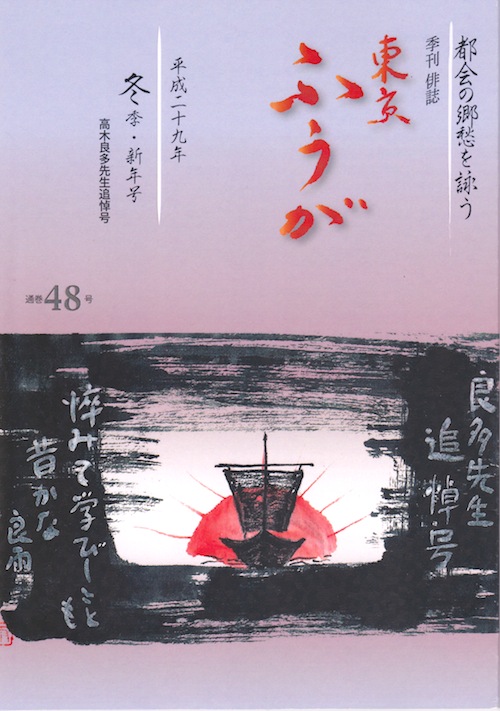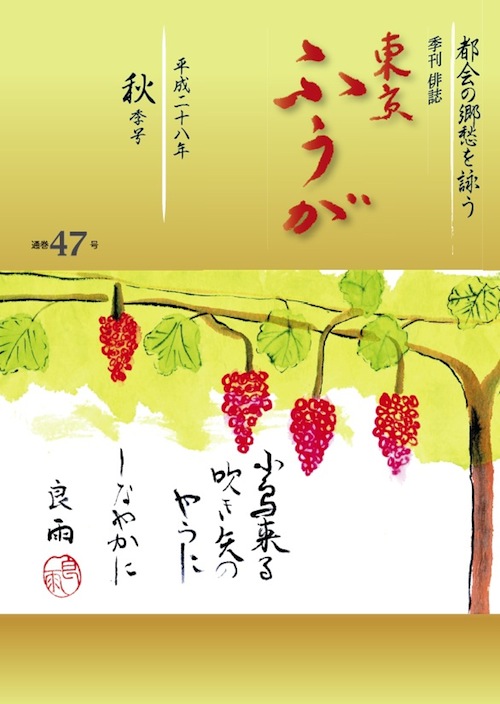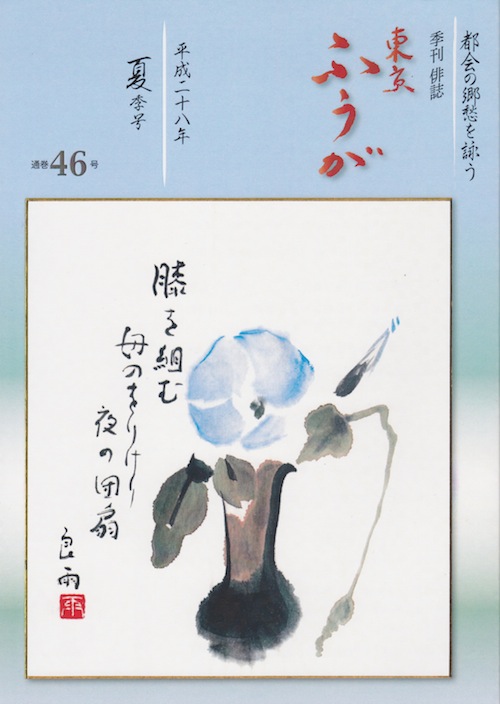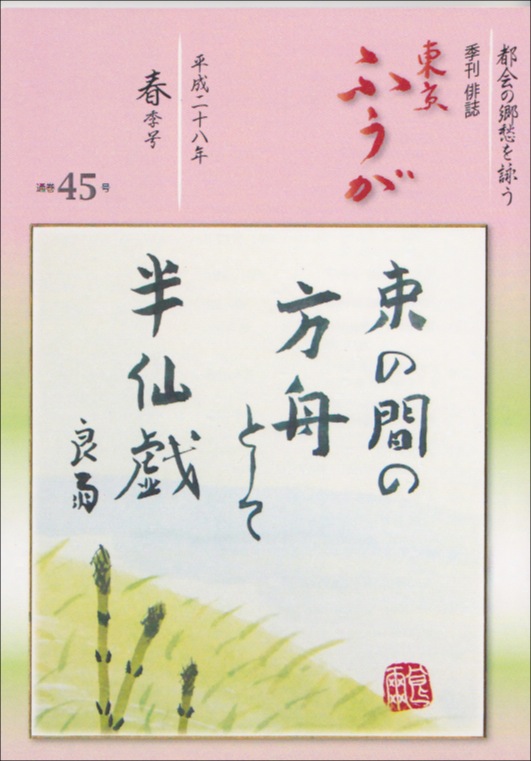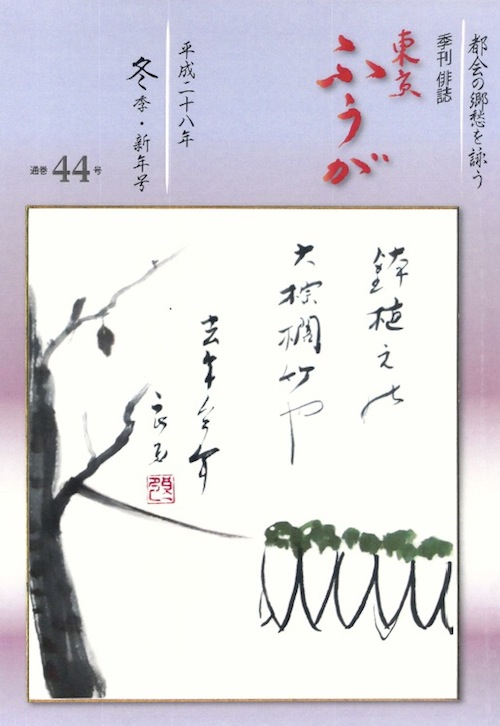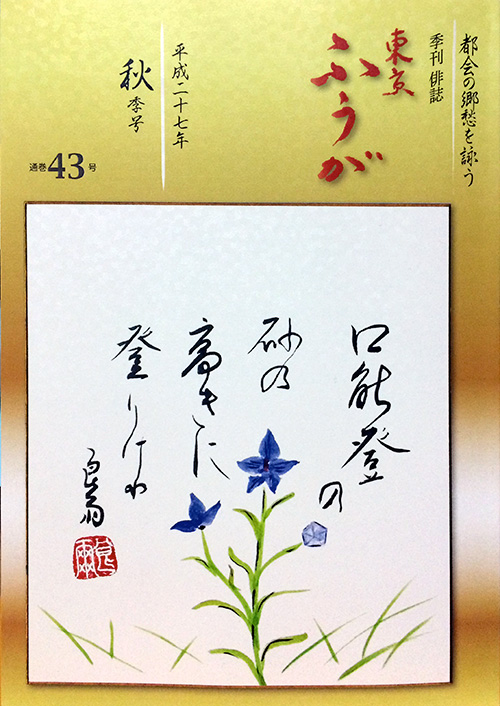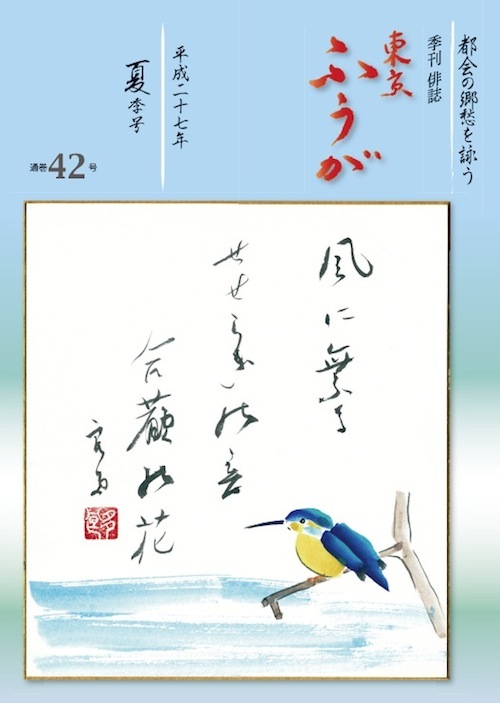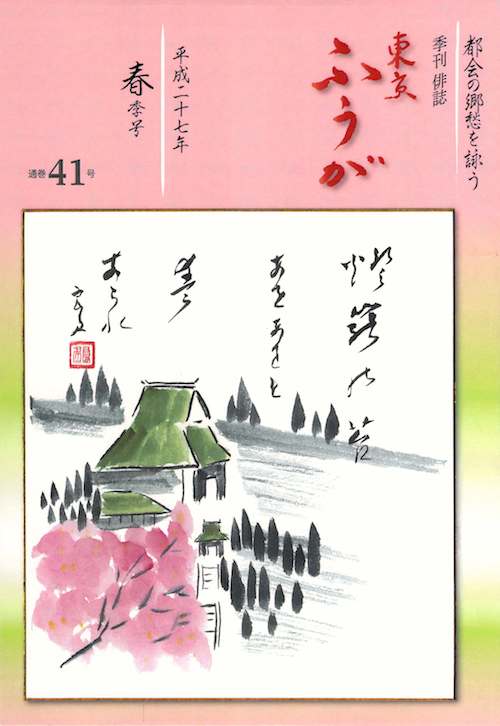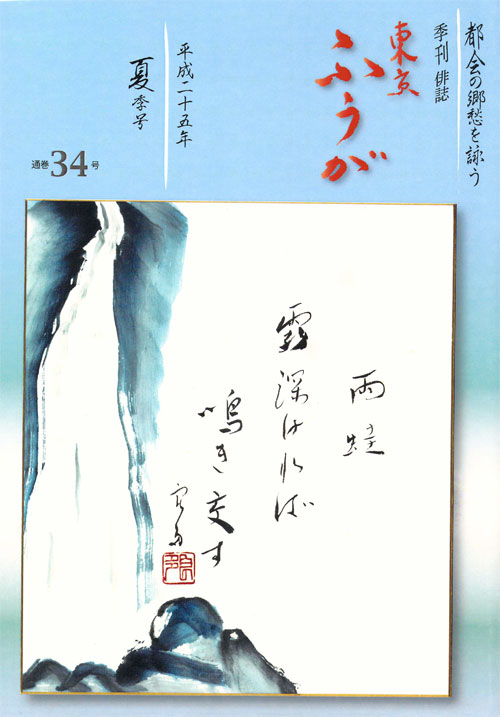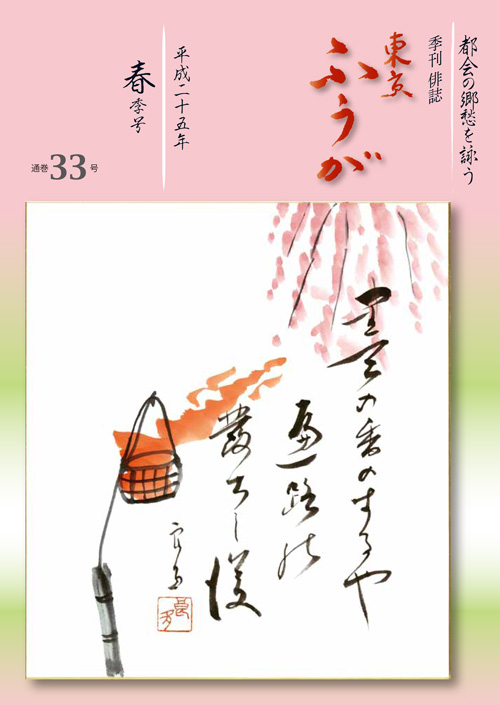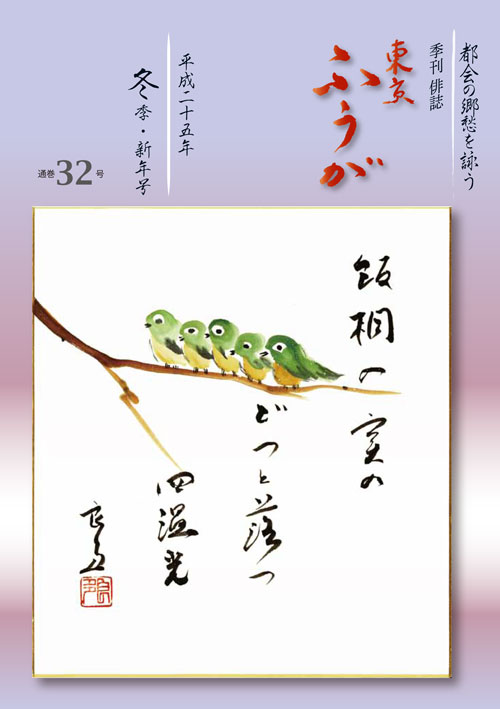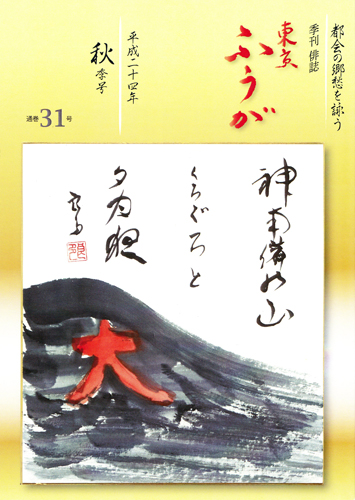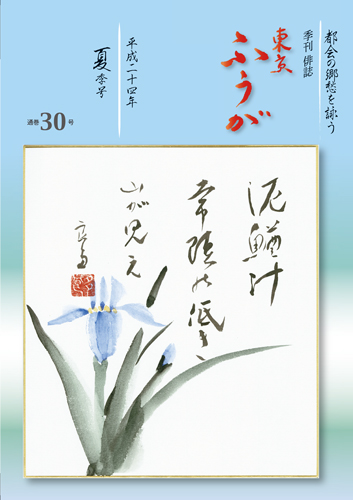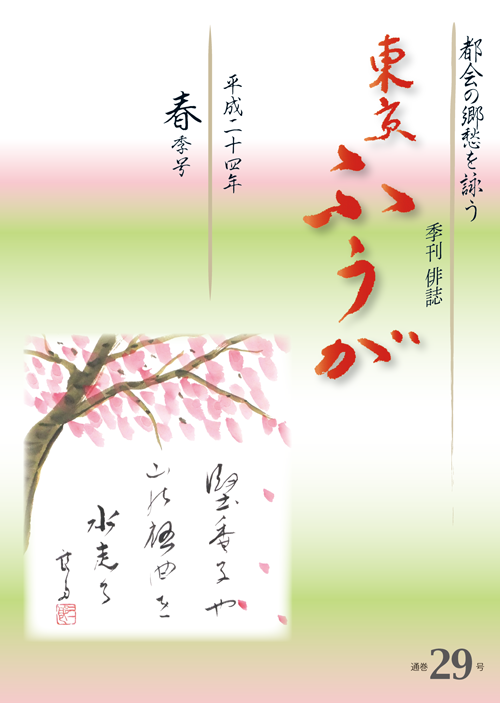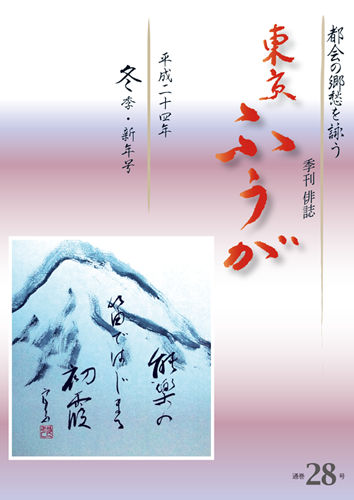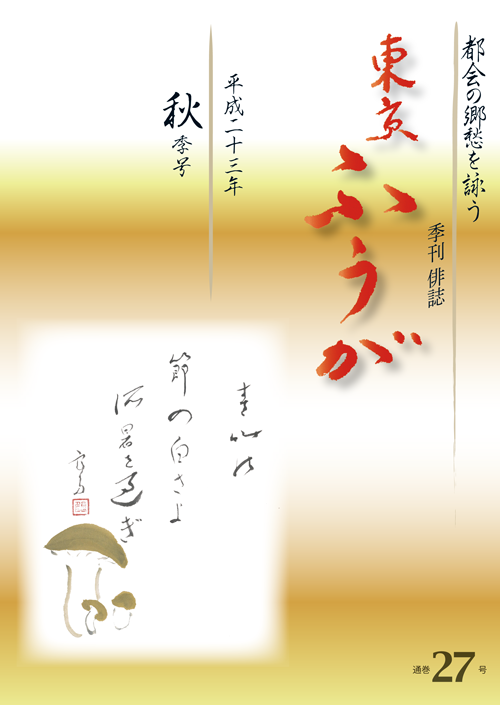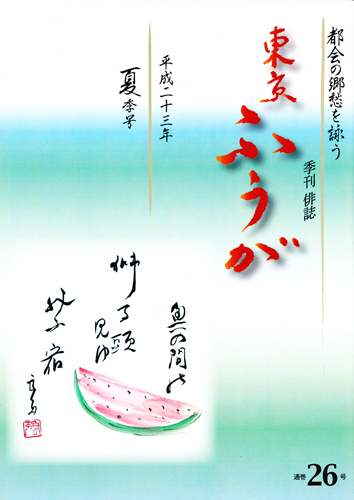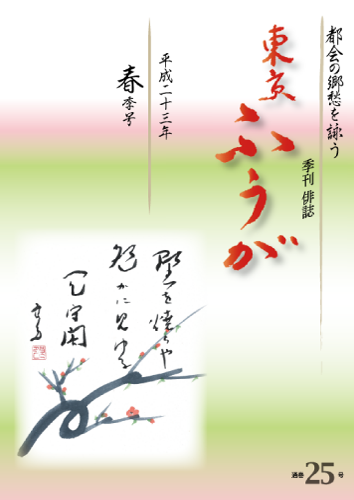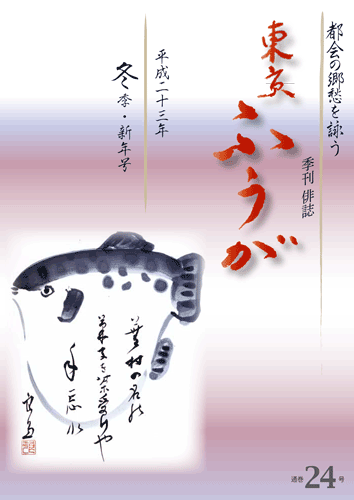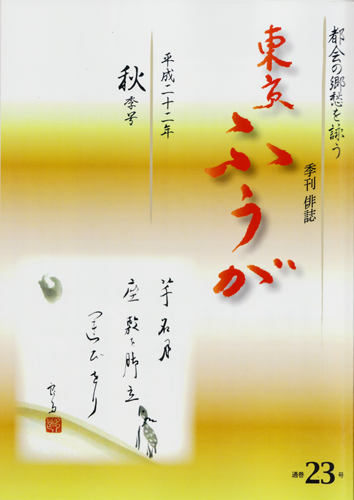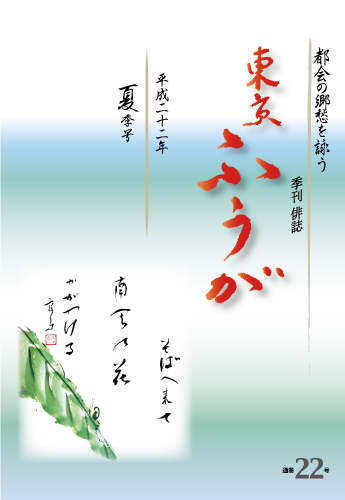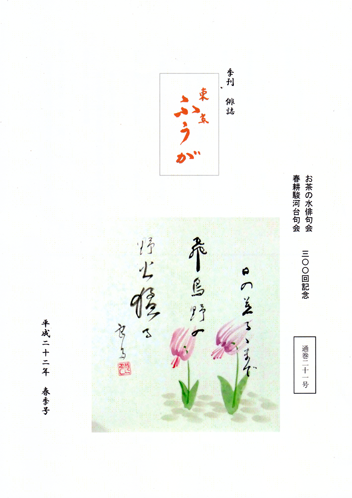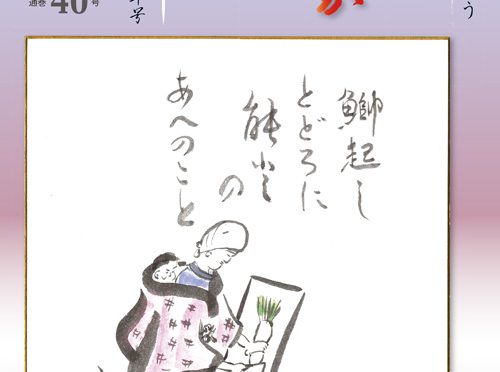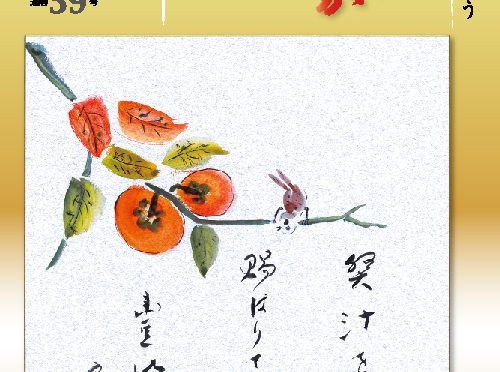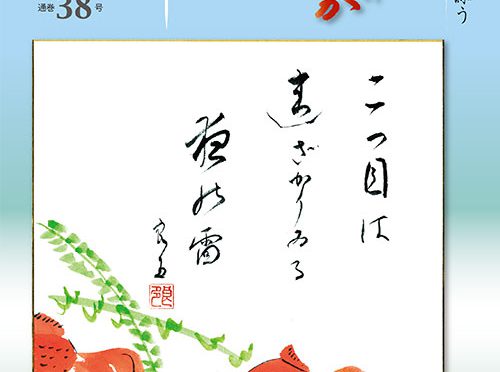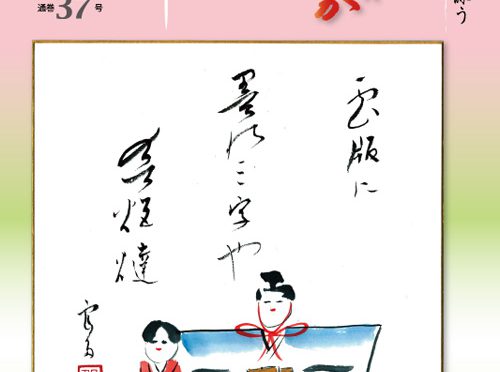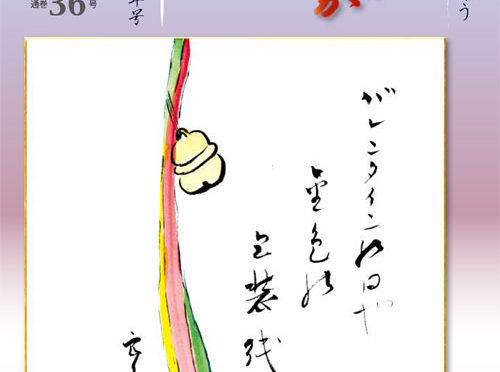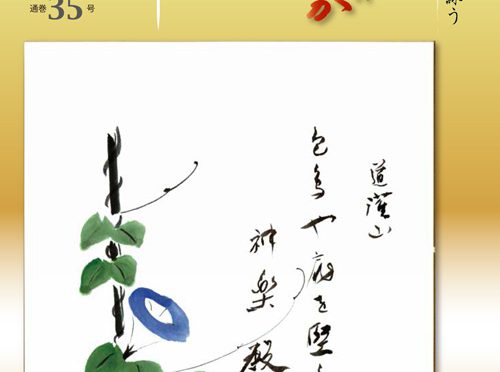「お茶の水俳句会」タグアーカイブ
蟇目 良雨 ● 東京ふうが 主宰
 昭和17年・埼玉県生まれ。
昭和17年・埼玉県生まれ。「春耕」主宰。
「塔の会」会員。俳人協会監事。
「お茶の水俳句会」指導。皆中句会指導。春耕同人ネット句会指導。神保町句会指導。
皆川盤水「春耕」・澤木欣一「風」に師事。
昭和63年 「春耕賞」。 続きを読む
高木 良多 ● 東京ふうが 顧問
東京ふうがバックナンバー
東京ふうが40号(平成27年冬季・新年号)
編集人が語る「東京ふうが」40号
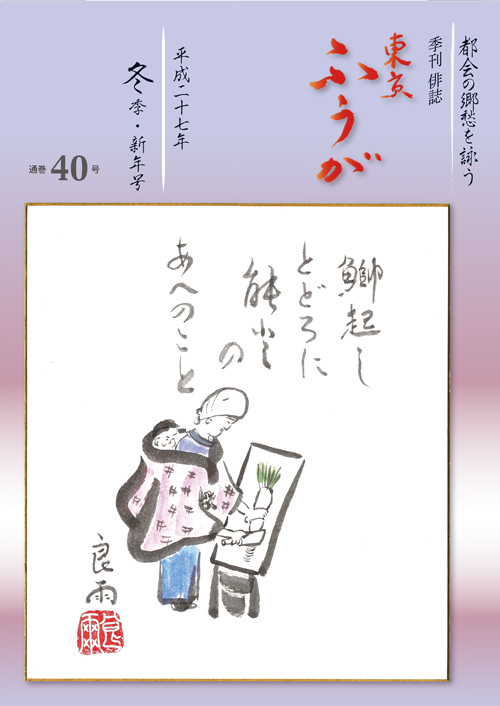 戦後間もなく発表された桑原武夫の「第二芸術論」を「俳句界」3月号、4月号で改めて読んだ。
戦後間もなく発表された桑原武夫の「第二芸術論」を「俳句界」3月号、4月号で改めて読んだ。
当時敏感に反応した秋櫻子や草田男。一方、「俳句も芸術と呼ばれるようになったのですか」と悠然と構えた虚子の2つの流れがあったが、70年前と事態は改善されたわけでもないことに気付かされた。
芸術と呼ばれたいのなら、人を感動させる句を作らなければならない。
桑原武夫を俳句の門外漢などと退けることなく謙虚に、再び考えることをしたい。
目 次
| 1 | 名句逍遥 | |
| 欣一俳句の鑑賞(19) | 高木良多 | |
| 良多俳句の鑑賞(19) | 蟇目良雨 | |
|
|
||
| 2 | 作品七句と自句自解「冬季・新年詠」ちょっと立読み | |
|
|
||
| 6 | 墨痕三滴(俳句選評) | 鑑賞:蟇目良雨 |
| (お茶の水句会報355回~358回より選んだもの) | ||
|
|
||
| 7 | 寄り道 高野素十論 < 11 >ちょっと立読み | 蟇目良雨 |
|
|
||
| 19 | 【特集】 菽水と蕪村ちょっと立読み | 高木良多 |
|
|
||
| 12 | 曾良を尋ねて < 23> | 乾 佐知子 |
| 「草の戸も」の句の真意 ほかちょっと立読み | ||
|
|
||
| 14 | 旅と俳句 新涼のハルビン・大連紀行<2>ちょっと立読み | 石川英子 |
|
|
||
| 17 | 八千草日記 | 高木良多 |
| (9) 山法師(やまぼうし)ちょっと立読み | ||
| (10) 藤の実 | ||
|
|
||
| 18 | 【新連載】 「遊ホーッ」 | 洒落斎 |
| 零の発明と五十音図の発明の起源ちょっと立読み | ||
|
|
||
| 19 | エッセイ 息栖神社と側高神社 参拝の記ちょっと立読み | 石川英子 |
|
|
||
| 22 | 秀句探索・読者からのお便り・ほか | |
|
|
||
| 24 | ふうが添削コーナー会友招待席ちょっと立読み | 高木良多 |
|
|
||
| 25 | 後 書 | 蟇目良雨 |
|
|
||
| 表3 | 東京ふうが歳時記 < 19 >【 冬季・新年 】 | 編集部選 |
|
|
||
東京ふうが39号(平成26年秋季号)
編集人が語る「東京ふうが」39号
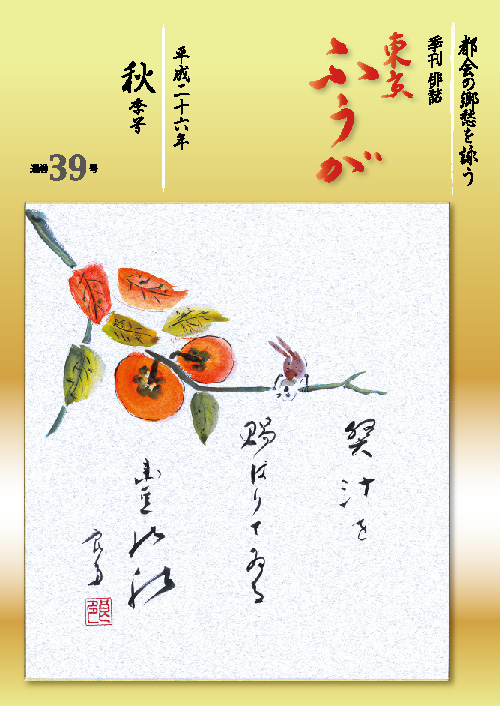 俳句に対する姿勢として「俳句ポケット論」がある。これは右のポケットに生業を入れ左のポケットに俳句を入れるという意味である。
俳句に対する姿勢として「俳句ポケット論」がある。これは右のポケットに生業を入れ左のポケットに俳句を入れるという意味である。
生活を支える仕事をきちんと持ってこそ心豊かな俳句が出来るという考えである。
確かにこういわれてみると著名俳人にはしっかりと仕事に業績を残している先人が多い。秋櫻子は医師、誓子は住友社員、風生は逓信官僚、素十も法医学者だ。例外は虚子であろう。最初から文藝で食おうとしている。そして少しも厭らしくない。小説家のように文筆に命を懸けている。
結局、どちらと言うことはできないのだろうが、自分が今、生活に困ればどんな句を作るのか興味がある。
目 次
| 1 | 名句逍遥 | |
| 欣一俳句の鑑賞(18) | 高木良多 | |
| 良多俳句の鑑賞(18) | 蟇目良雨 | |
| 2 | 作品七句と自句自解「秋季詠」ちょっと立読み | |
| 6 | 墨痕三滴(俳句選評) | 鑑賞:蟇目良雨 |
| (お茶の水句会報352~354号より選んだもの) | ||
|
|
||
| 7 | 寄り道 高野素十論 < 10 >ちょっと立読み | 蟇目良雨 |
| 14 | 曾良を尋ねて < 22> | 乾 佐知子 |
| 『奥の細道』までの道程 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲちょっと立読み | ||
| 17 | 旅と俳句 新涼のハルビン・大連紀行ちょっと立読み | 石川英子 |
| 21 | 八千草日記 | 高木良多 |
| (7) 螢 袋(ほたるぶくろ)ちょっと立読み (8) 蓮華升麻(れんげしょうま) |
||
| 23 | 沢木太郎編 『沢木欣一全句集』の読後感 | 高木良多 |
| 25 | エッセイ 晩秋の香取 伊能忠敬の墓など | 石川英子 |
|
|
||
| 26 | 読者からのお便り | |
|
|
||
| 28 | インフォメーション 他誌掲載作品 | |
| 角川『俳句』10月号 我が夜長 | 蟇目良雨 | |
| 月刊『俳句会』10月号 沙羅落花 | 高木良多 | |
|
|
||
| 30 | 会友招待席(会友句鑑賞)ちょっと立読み | 高木良多 |
|
|
||
| 31 | 後 書 | 蟇目良雨 |
|
|
||
| 表3 | 東京ふうが歳時記 < 18 >【 秋 】 | 編集部選 |
|
|
||
東京ふうが38号(平成26年夏季号)
編集人が語る「東京ふうが」38号
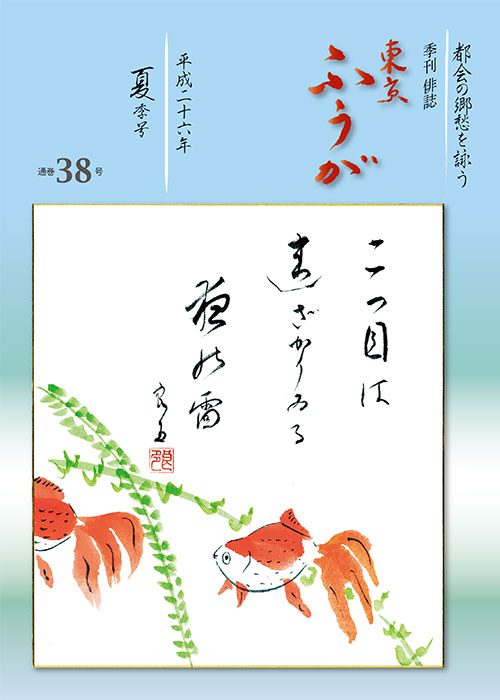 高野素十と水原秋櫻子の「自然の真と文芸上の真」論争でその引き金を引いたと言われる俳誌『まはぎ』に掲載された論文はどんな内容なのか、それほど秋櫻子を傷つけたのか大変曖昧である。本号ではその『まはぎ』に焦点を当ててみた。読者のお役に立てば幸いである。
高野素十と水原秋櫻子の「自然の真と文芸上の真」論争でその引き金を引いたと言われる俳誌『まはぎ』に掲載された論文はどんな内容なのか、それほど秋櫻子を傷つけたのか大変曖昧である。本号ではその『まはぎ』に焦点を当ててみた。読者のお役に立てば幸いである。
なお、発行人が高木良多先生から蟇目良雨に交代した。先生ご高齢のためにお申し出がありここにご報告する。
蟇目良雨
目 次
- 1 名句逍遥
- 欣一俳句の鑑賞(17) 高木良多
- 良多俳句の鑑賞(17) 蟇目良雨
- 2 作品七句と自句自解「夏季詠」 ►ちょっと立読み
- 6 墨痕三滴(俳句選評) 鑑賞:蟇目良雨
- (お茶の水句会報349~351号より選んだもの)
- 7 八千草日記 高木良多 ►ちょっと立読み
- (5) 岩煙草(いわたばこ)
- (6) 蕺 草(どくだみ)
- 8 寄り道 高野素十論 < 9 > 蟇目良雨 ►ちょっと立読み
- 18 東京大空襲体験記 銃後から戰後へ <30> 鈴木大林子
- 「白内障手術体験記」 ►ちょっと立読み
- 20 曾良を尋ねて < 21> 乾 佐知子
- 59 安宅丸と堀田正俊の刺殺まで ►ちょっと立読み
- 60 安宅丸と堀田正俊の刺殺まで ②
- 61 堀田正俊の刺殺とその後
- 23 子規の滑稽俳句を探る 蟇目良雨 ►ちょっと立読み
- 26 高幡不動の歴史 高木良多
- 27 書評「俳句探訪」 山口耕堂
- 22 会友招待席(会友句鑑賞)
- 「鑑賞と添削」 高木良多 ►ちょっと立読み
- 24 後書 高木良多
- 24 句会案内
- 表3 東京ふうが歳時記 < 17 >【 夏 】 編集部選
東京ふうが37号(平成26年 春季号)
編集人が語る「東京ふうが」37号
 安倍内閣の集団的自衛権行使への道筋がなし崩しに付けられている昨今ですが、戦前もいつの間にか戦争への道筋がつけられたのかと思うと恐ろしくなります。
安倍内閣の集団的自衛権行使への道筋がなし崩しに付けられている昨今ですが、戦前もいつの間にか戦争への道筋がつけられたのかと思うと恐ろしくなります。
考えないという態度が国を危うくするのでしょう。
子や孫の時代に不幸な思いをさせないように正しい道を考え、探し続けましょう。俳句の道に於いても。
蟇目良雨
目 次
- 1 名句逍遥
- 2 作品七句と自句自解「春季詠」 ►ちょっと立読み
- 6 墨痕三滴(俳句選評) 添削:高木良多
- 7 八千草日記 高木良多 ►ちょっと立読み
- 8 寄り道 高野素十論 < 8 > 蟇目良雨 ►ちょっと立読み
- 10 東京大空襲体験記 銃後から戰後へ <29> 鈴木大林子
- 11 曾良を尋ねて < 20> 乾 佐知子
- 13 「旅と俳句」梅里雪山の旅< 最終回 > 石川英子
- 22 会友招待席(会友句鑑賞)
- 24 後書 高木良多
- 24 句会案内
- 表3 東京ふうが歳時記 < 16 >【 春 】 編集部選
東京ふうが36号(平成26年 冬季・新年号)
編集人が語る「東京ふうが」36号
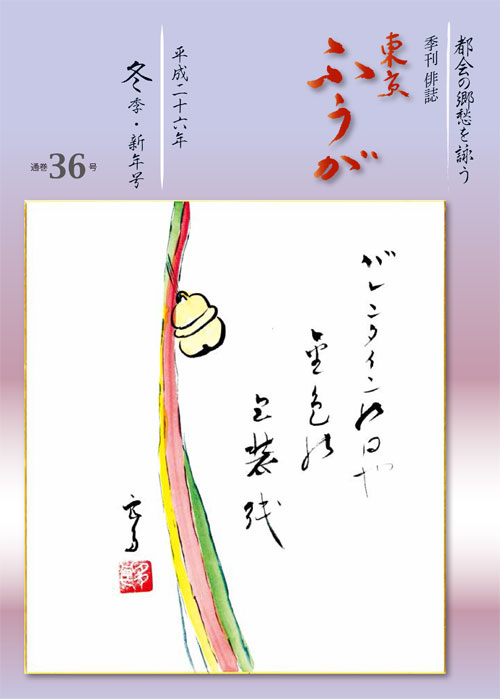 子規が35歳で逝き、芭蕉が50歳で逝き、一茶は65歳で逝き、蕪村が68歳で逝きと没年を書き連ねてみたのは、一家をなした先人のことをしきりに思うからである。
子規が35歳で逝き、芭蕉が50歳で逝き、一茶は65歳で逝き、蕪村が68歳で逝きと没年を書き連ねてみたのは、一家をなした先人のことをしきりに思うからである。
蕪村をも超えて馬齢を重ねている己を叱咤して「東京ふうが」に力を注入しつづけたい。
蟇目良雨
目 次
- 1 名句逍遥
- 2 作品七句と自句自解「冬季・新年詠」 ►ちょっと立読み
- 6 墨痕三滴(俳句選評) 添削:高木良多
- 11 曾良を尋ねて < 19> 乾 佐知子
- 13 「旅と俳句」梅里雪山の旅< 2 > 石川英子
- 21 「澤木欽一の行脚風景」発行の顛末 高木良多 ►ちょっと立読み
- 22 会友招待席(会友句鑑賞)
- 24 後書 高木良多
- 24 句会案内
- 表3 東京ふうが歳時記 < 15 >【 冬季・新年 】 編集部選
東京ふうが35号(平成25年 秋季号)
編集人が語る「東京ふうが」35号
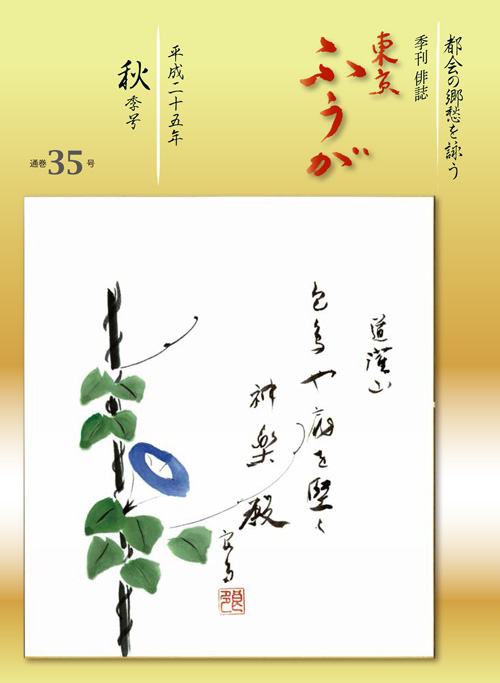 高木良多が連載していた澤木欣一の句集研究が一冊に纏まり、『俳人澤木欣一 行脚の風景』として出版された。
高木良多が連載していた澤木欣一の句集研究が一冊に纏まり、『俳人澤木欣一 行脚の風景』として出版された。
また、蟇目良雨の「寄り道 高野素十論」は四Sと呼ばれた高野素十の絶頂期に何が起こったかを研究。虚子と素十と秋櫻子の微妙な関係を描いて興味尽きない。
乾佐知子の「曾良を尋ねて」は、芭蕉が深川へ引退したのは綱吉将軍就任の際のトバッチリを受けてのことという説を引用しハラハラドキドキになる。
このほかの読み物と俳句も都会の哀愁を掬い稀有な俳句集団と言えるだろう。
蟇目良雨
目 次
- 1 名句逍遥
- 2 作品七句と自句自解「秋季詠」 ►ちょっと立読み
- 6 墨痕三滴(俳句選評) 添削:高木良多
- 7 【寄り道 高野素十論】< 6 > 蟇目良雨 ►ちょっと立読み
- 11 東京大空襲体験記 銃後から戰後へ <27> 鈴木大林子
- 13 曾良を尋ねて < 18> 乾 佐知子
- 15 「旅と俳句」梅里雪山の旅< 1 > 石川英子
- 18 小林螢二さんご遺族・小林和子さんの手紙から
- 19 卒寿祝ノ謝辞 高木良多 ►ちょっと立読み
- 20 会友招待席(会友句鑑賞)
- 21 後書 高木良多
- 22 句会案内
- 表3 東京ふうが歳時記 < 14 >【 秋季 】 編集部選